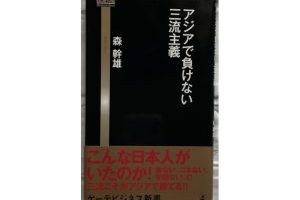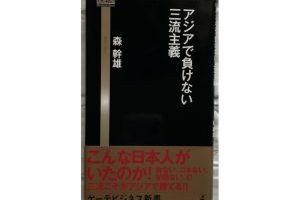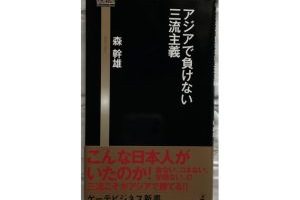2025.05.05
「金なし、コネなし、学歴なし」⸺“三流”だからこそ勝てたアジアビジネスのリアルを描いた一冊、『アジアで負けない三流主義』。引き続きお楽しみください。
前回#9の内容を読みたい方はこちら!
#1から読みたい方はこちら!
第7章 アホであれ
貧困や病気体験はエネルギーになる
困難を克服するには
あれこれと批判する人が尊いわけではない。
実力者がなぜ失敗したのかとか、実行者はもっとうまくやるべきだったなどと、指摘する者が偉いわけではない。
賞賛に値するのは、実際に行動した男であり、汗と血でまみれ、勇敢に戦い、何度も間違いを犯して成功にまで手が届かなかった男であり、熱意を持って身を捧げ、有意義な目標に向かって全精力を使い、たとえ失敗したとはいえ果敢に挑戦した男である。
その人物は、勝利も敗北も知らない臆病者たちとは一線を画している。
これは、私が大好きなアメリカ合来国の第26代大統領、セオドア・ルーズベルトの言葉だ。
「このルーズベルトの言葉にある“男”のように生きたい」ずっと思い続けてきた。そして、今なお思っている。
あまたの自伝や歴史書を読むと、分野にかかわらず、多くの成功者に共通する条件がある。それは、幼少期から青年期にかけてのどこかの時期に貧困、もしくは病気などの辛い体験をしているということだ。アスリートを例にとってみても、子どもの頃に貧しい環境で育った選手は多い。ルーズベルトは裕福な家庭で育ったものの、ぜんそくに苦しみ、幼少期の大半をベッドの上で過ごしている。
こうした思いがけない苦しみによって、困難を克服する力が養われるのだ。そして、その状況が改善されていく過程で、人間の持つ力や温かさを知ることにもなる。
これが、いわゆる“ハングリー精神”が育つプロセスだ。
こういうタイプの人間が豊かになると、得たものを大切にして育てていく。慎重に慎重にとことを運ぶ。ないことの苦しみが身にしみているからだ。ない時代の自分に戻りたくないからだ。ない時代を経験している人間は、だから強い。さらなる努力を積み重ねていく。
「倒産」「闘病」「投獄」
昔から日本では、歴史に名を残す経営者、成功者はこの三つの「トウ」のいずれか、もしくは複数を経験していることが多いそうだ。
必ずしもこの三つに該当しないまでも、人は大きなハンディキャップやコンプレックスを持つことで、それをエネルギーに転換してことを成し遂げるものだ。
いずれも退路を断たれるからだろう。そのとき、人は信じられない力を発揮することができるのだ。
アタマがいいから使われる
アホであれ
私は気づいたことがある。
「オレはアホが幸いしたんじゃないか?」そう思うのだ。
学歴や偏差値など、世間一般の基準では、私は最低レベルだ。語学など生活のなかで身につけたものはあるが、デスクの上で行うような実務の能力も低い。
「パソコン?よう使えまへん」
「エクセル?それ、なんでっか?」
「パワーポイント・・・・・・?」
そんな感じだ。
だから、私には誰も何も期待しない。使えないからだ。それで、人に使われずに生きてこられた。
実務能力が優れていると、重宝がられる。みんなが集まってきて、いろいろと頼んでくるだろう。でも、私にはそういう経験などない。
逆に、こちらは何もできないから、知恵を働かせて人に仕事をさせようとする。ある時期からは人に任せることもできるようになった。それが、経営につながっているような気がしている。
「オレ、小器用でなくてよかったなあ」つくづく思う。
「一流大学を出ていなくてよかったなあ」心からそう思う。
要するに賢いから人に使われるのだ。勉強ができて一流大学に入っても、結局は使われる人生。私はアホだから、アタマのいい人を使えるのだ。
先日、亡くなったアップル社のスティーブ・ジョブズの伝説のスピーチの一節に「Stay Hungry, Stay Foolish」(ハングリーであれ、アホであれ)とあるが、まったくその通りだと思う。
絶対にできる
自分に言葉をかけて奮い立たせる
最後に、私が好きで、生きる活力にしている言葉を紹介したい。
「三流主義」
第1章にも書いたが、これこそ私自身である。学歴もなく、お金もなく、コネもなく、二枚目にはほど遠い容姿の三流だからこそ、「こんちくしょう!」という思いで、ここまで頑張ってこられたし、これからも努力を続けていける。
「何百年もの間、羊として生きるよりも、一日でもライオンとして生きるほうがましだ」イタリアのことわざだ。ライオンを見ていると元気になれる。
中国の『史記』にある「鶏口(けいこう)となるも牛後(ぎゅうご)となるなかれ」も同じ意味だが、私はどんな場所、組織、チームでも常に長でありたいと思っている。これは私の生き方そのものなのだ。
「明日死ぬつもりで生きなさい、未来永遠に生きるつもりで学びなさい」非暴力を貫いたインドの独立運動家、マハトマ・ガンディーの言葉だ。
本当に死ぬつもりで行動すれば、必ず道が開けることを教えてくれている。新しいビジネスを興すとき、新たな土地に行ったとき、私はこの言葉を肝に銘じ、覚悟する。
覚悟さえあれば、できないことはない。
「エベレストはこれ以上高くはならないが、私は必ず成長できる」
私が生まれた年の1953年に世界で初めてエベレスト登頂に成功したニュージーランド人、エドマンド・ヒラリー卿の言葉だ。ヒラリー卿がエベレスト登頂に失敗したときに発したという。
私は毎年正月に自分の目標を立て、年末に一年をふり返り、反省をする。今までに、目標が100%達成されたことは、一度たりともない。
しかし、100%達成されるような目標だったとしたら、それは設定が甘かったと思うべきだ。常に高いところを見て、そこに向かって努力を重ねてこそ、成長がある。
私の目標は常に具体的だ。そして、その目標を達成した自分を常にイメージし、そこから逆算して今日を生きる。
そして最後になるが一番大切にしている言葉がこれだ。
「頑張り屋さんのあんたなら絶対できる!」
これは、前にも書いたが、シンガポールに渡る前に、母が私にかけてくれた言葉である。これほど私を勇気づけ、奮い立たせる言葉はない。
「絶対できる!」
私は、母からの言葉を毎日自分に言い聞かせている。
そうやって毎日を闘ってきた。
よく、企業の寿命は30年といわれるが、クラウンライン・グループは45年目を迎える。それも、常に退路を断ち、そして、毎日「絶対できる!」と思い続けた積み重ねの結果だと思っている。
おわりに
現在の日本はジリ貧だ。財政赤字は深刻で、日本の借金(国及び地方の長期債務残高)は約868兆円(2010年末時点。財務省調べ)。1家族当たり約1,730万円となり、要するに今日オギャーと生まれた赤ちゃんも、生まれたと同時に約683万円の借金を背負っていることになる。
また、日本の失業率は4.7%(2011年7月現在。総務省調べ)。労働人口の20人に1人が失業している計算だ。この失業率には、実はからくりがある。日本における失業者の定義は「働く意思と能力があるにもかかわらず職に就けない人」だ。つまり、失業者にはホームレスは含まれていない。だから、実質的な失業者は4.7%どころではない。
事実、50歳未満の男性の80%以上が年収400万円未満と聞く。加えて、年金は破綻。
将来がまったく見えず、閉塞感に満ちている。
巷には一所懸命勉強をして、偏差値の高い大学で教育を受けても、就職口が見つからない新卒者が溢れているらしい。運よく、就職できたとしても、その仕事に将来を見いだせず、すぐに辞めてしまうらしい。
若者が失望感で自暴自棄になってしまうのもよくわかる。だからこそ思う。
「お前ら、このままでいいんか?」
「お前ら、この国だけを仕事の舞台に働いていて大丈夫なんか?」
頑張る気持ちがあっても働く機会を得ることができない日本の20代、30代を憂慮して、「オレに連絡をくれ!」と呼びかけているのだ。
海の向こう、シンガポールを拠点にアジア各国で仕事をしているからだろう。私には、帰国のたびに日本のジリ貧状況がくっきりと見える。1か月に1度のペースでこの国へ戻ると、前月よりも元気がなくなっていることがよくわかるのだ。
心がささくれだった若い人も多い。
先日、東京でのこと。JRの3人がけのシートに座っていると、隣に20代後半のサラリーマンが二人分のスペースを占領して座っていた。両脚をポーンと前に投げ出してい
る。
「行儀の悪い兄ちゃんやなあ」
そう思いながらも、とりあえずは黙って座っていた。
それからいくつ目の駅だっただろう。70代くらいの女性が一人、私たちの前に立った。
とっさに席を譲ろうと思ったが、まてよ、隣の兄ちゃんがマナーを守って一人分のスペースに座ればいいんじゃないか。すぐに気持ちを切り替えた。
「君、もう少し脇にずれて、このご婦人に座ってもらおうよ」私にしては丁寧な口調で提案した。しかし、聞こえないふりをしている。しかたがないので、もう一度提案した。
「お兄ちゃん、少しずれてあげようよ。仲よく3人で座ろう」すると、今度はめんどうくさそうに尻をずらした。女性は私たちに頭を下げてお礼を言い、あいたスペースに腰かけた。その時「チッ!」という兄ちゃんの舌打ちが聞こえた。一瞬ムカッときた。でも、私も分別のある大人である。気持ちよく座っている女性のことを思い、怒りを飲み込んだ。
女性、私、兄ちゃんの順番で、3人がけのシートに並び、電車は走っていく。
気づくと、隣に座る兄ちゃんが、ブツブツ何か言っている。
「ざけんじゃねえよ…・・・・」私の耳には、そう聞こえた。
「兄ちゃん、文句があるんなら、ちゃんと聞いてあげるから、どこの駅で降りるか教えてや。一緒に降りて話そうや。この電車の中ではダメやで。黙っとこう。隣の人は、オしたちに親切にされたと思って気持ちよく座ってはるんや。その感謝の心を裏切っちゃあかん」
耳元で、ささやいた。それから、またいくつか駅を過ぎた頃、お兄ちゃんに念押しをした。
「いいかい、降りるときにはオレに言えよ。こちらはいくらでも時間はある。ゆっくり話を聞いてやるから」
しかし、結局、その兄ちゃんと話すチャンスはなかった。電車が次の駅に着くと、ドアが閉まる間際にいきなり席を立って逃げてしまったからだ。
気が弱いのはしかたがない。それを責めるつもりはない。でも、逃げるならば、強がったりしなければいいのだ。
そして、その兄ちゃんがホームを走っていく姿を見て、同じ車両に乗っている人たちは笑っていた。しかし、そいつらだって、逃げたサラリーマンと同じだ。乗車態度の悪い彼を目にしても見て見ぬふりをしていたのだから。
「お前ら、人のこと、笑える身か?」そう思った。
「日本もセコい国になったなあ」寂しい気持ちになった。
生活に、人生に、希望が持てなくなると、人間の気持ちはかさかさしてくる。
品川駅前のタクシー乗り場でもこんなことがあった。
知人と二人で両手に荷物を抱えて並んでいると、後ろから押してくるヤツらがいる。
「荷物持っているんだから、僕たちは早くは前に進めないんや。そんな慌てないで、待ったってよ」
そう言ってふり返ると、やはり20代後半くらいのサラリーマンが4人。酒が入っているのだろう。みんな顔が赤い。
「もう少しだから、君たち、辛抱してや」もう一度言って、やがてやってきたタクシーに乗り込んだ。
すると、タクシーのドアが閉まりかけたそのときだ。4人組のうちの一人が、私に向かって中指を立てて「ファック・ユー」と言ったのだ。
人にはやっていいことと、絶対にやってはいけないことがある。彼の言動は、明らかに後者だ。
人には許すべきことと、絶対に許してはいけないことがある。私がとるべき態度は、明らかに後者だ。
「ちょっと待っていてください」
ドライバーにひと言告げるやタクシーを降り、私は中指を立てた男のこめかみに拳をのめりこませた。羽交い締めにしてきた男にはひじ打ち、あとの二人にはそれぞれ腹に蹴りと胸にパンチを入れて、戦意喪失したのを確認してタクシーに乗り込んだ。
興奮していたので気がつかなかったが、こちらもけっこうやられていて、高価なヴェルサーチのスーツがボロボロに破れていた。
彼らは4人。自分たちが数的に有利だから、強い態度に出たに違いない。こちらが50代のオッサンだから、なめてもいただろう。その根性も許せなかった。
「日本はセコい国になったものだ」そのときにも感じた。
ここ何年のことだろうか。日本に戻ると、信じられないような事件ばかりが起きている。未成年者による殺人、親殺し、子殺し・・・・などが立て続けに新聞やテレビのニュース番組で報道されている。私が子どもだった頃は聞いたこともなかった事件ばかりだ。
こうした事件も、私が遭遇したセコい若者たちの行動も、背景には同じものが見える。
希望がないという現実だ。人は、希望を持てないと苛立つ。そして、心がささくれ立ち、攻撃的な性格になっていく。
昭和30年代、高度経済成長期の日本は、発展途上国だった。今よりもはるかに貧しかった。でも、希望はあった。だから、今のようなゆがんだ事件は少なかったのではないか。
希望を持てず、苛立ちを抑え、体の中にマグマのようにエネルギーを蓄えている若い人たちは多い。彼らの心がダメになる前に、国は希望を持たせなくてはいけない。
しかし、今の日本には余力がない。100年に一度といわれる出口の見えない不況のなか、あの3.11の東日本大震災が起きてしまった。国をあてにせず、自分の力で自分の人生を切り拓いていかなくてはいけない。
その選択肢の一つとして、今成長著しいアジアに出て仕事をしてもらいたいと、私は日本に戻るたびに強く感じているのだ。
沈み行く日本ではなく、元気なアジアへ。
この本を読んで、アジアで勝負しようと思う人が一人でも増えてくれたら嬉しい。
最後に、私のような裸一貫でアジアに飛び込んだ者を言じ、ついてきてくれた社員に感謝したい。彼らこそが次代のアジアを背負うリーダーだ。また、この本を出版するきっかけを与えてくれ、サポートしてくれた梶田泰司さん、中込知野さんに、また実際の執筆においては多大なるアドバイスをくださった神舘和典さん、編集の八木基之さんに感謝をしたい。そして、勝手ながら、この本を妻SAMINATH(サミナ)と母森迪子(もりみちこ)に捧げることを許していただきたい。
籍を入れたとき、結婚式も挙げてあげられず、ハネムーンにも連れて行ってあげられなかった妻。今まで常に寄り添ってくれてありがとう。次男の挙式と一緒に今秋、30年以上経って初めて挙げた私たちの結婚式は、生涯忘れられない思い出になった。
そして母。いつも勝手ばかりで、どんなに心配をかけたことか。今の自分があるのは、母のおかげ以外なにものでもない。
偉大で清らかで美しいお母ちゃん、20数年しか一緒に暮らしていないけど、一時も忘れたことはありませんでした。本当にありがとう。どうかもっと長生きしてください。
2011年11月シンガポールにて

著者:森 幹雄(もり みきお)
クラウンライン・グループ社主・CEO
海外日系新聞放送協会副会長
アジア経営者連合会理事
シンガポール日本人会理事
1953年京都府生まれ。工業高校卒業後、日立製作所入社。退社後、アメリカを経て、単身シンガポールへ渡る。外資系引っ越し会社に3年間勤務後、日本人による日本人のための海外引っ越し専門会社クラウンラインを設立。今では11か国21都市に進出する。本業以外にも出版・情報サービス、イベント企画などを展開中。
アジアビジネス実践塾 www.sg-biz.com
✉:mori@comm.com.sg まで、お気軽にご連絡を!