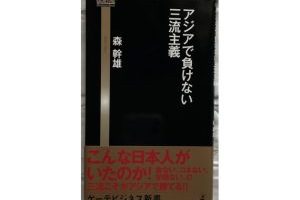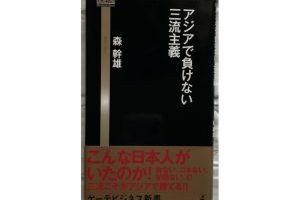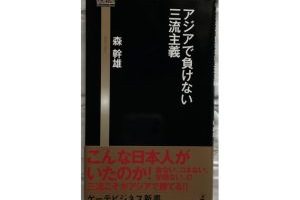2025.05.05
「金なし、コネなし、学歴なし」⸺“三流”だからこそ勝てたアジアビジネスのリアルを描いた一冊、『アジアで負けない三流主義』。引き続きお楽しみください。
前回#8の内容を読みたい方はこちら!
#1から読みたい方はこちら!
第6章 アジアビジネス成功の秘訣10か条
31年成長してきた理由はこれだ!
成功の秘訣10か条
ここで、クラウンライン・グループの創業からこの本を書いている2011年11月までの31年の歴史を紹介したいと思う(ここでは現在でも継続している事業のみ記述することにする)。
1980年
シンガポールに、海外引っ越し会社「クラウンライン」設立。
1981年
シンガポールに、運輸倉庫会社「アジア・パシフィック・エキスプレス」設立。
1984年
マレーシアに、海外引っ越し会社「クラウンライン・マレーシア」設立。
1987年
マレーシアに、運輸倉庫会社「Cライン・ホールディング」設立。
1989年
「クラウンライン・マレーシア」ペナン支店開設。
1991年
シンガポールに、出版・情報サービス会社「COMM」設立。生活情報誌『ハローシンガポール』創刊。
マレーシアに、出版・情報サービス会社「CEMアジア」設立。生活情報誌『ハローマレーシア』創刊。
1992年
タイに、出版・情報サービス会社「COMM・バンコク」設立。生活情報誌『ハロータイランド』創刊。
1994年
「クラウンライン・マレーシア」ジョホールバル支店開設。
1996年
マレーシアに、海外居住者へのサービス会社「クラウンライン・エクスパトリエイト・サービス」を設立。
マレーシアにて、日本語エンタメ情報誌『パノーラ』創刊。
インドネシアに、海外引っ越し、出版・情報サービス会社「チャヤリンタス・セメラン」を設立。
1997年
シンガポールにて、月刊情報誌『マハマハ(マハリクマハリカ)』創刊。
1998年
香港に、「クラウンライン・香港」を設立。生活情報誌『ハロー香港』を創刊。
シンガポールの「COMM」が、日本語FM放送『ハローシンガポールFM96.3』放送をスタート。
シンガポールで、倉庫業を主体とする「ユニオン=クラウン・ディストリセンター」をジュロンに設立。
1999年
台湾に、出版・情報サービス会社「クラウンヴァンライン」設立。生活情報誌『ハロー台湾』創刊。
シンガポールの月刊情報誌『マハマハ(マハリクマハリカ)』を『J-PLUS』に改名。
2000年
タイに、海外引っ越し会社「CLCムーヴァーズ」を設立。
2001年
「チャヤリンタス・セメラン」スラバヤ支店を開設。
2002年
中国に、「クラウンライン・中国」を設立(上海)。
2003年
ベトナムにて、書籍『ベトナム日系企業年鑑』を発行。
中国にて、生活情報誌『ハロー上海』を創刊。
2004年
東京に、リロケーションサービス会社「R&R」 設立。
中国に、「上海藍冠広告有限公司」設立(上海)。「クラウンライン・中国」広州支店開設。「クラウンライン・中国」北京支店開設。
インドネシアに月刊情報誌『さらさ』創刊。
シンガポールとマレーシアに週刊誌『J-SPORTS』創刊。
2005年
中国にて、生活情報誌『ハロー北京』創刊。
「チャヤリンタス・セメラン」から海外引っ越し部門を分社化、「クラウンライン・インドネシア」をジャカルタに設立。
2006年
インドにて、書籍『インド日系企業年鑑』を発行。
東京に、トレーディング会社「M&M」設立。
「クラウンライン・中国」大連支店開設。
2007年
中国にて、生活情報誌『ハロー華南』創刊。
ベトナムにて、生活情報誌『ハローベトナム』創刊。
2008年
シンガポールにて、子育て情報誌『ハローキッズシンガポール』創刊。月刊誌『J-Plus』から、隔週刊誌『J+PLUS』に新創刊。
2009年
ドバイに海外引っ越し会社「クラウンライン・UAE」開設。
ベトナムにて、海外引っ越し会社「クラウンライン・ジョイントストックカンパニー」ハノイ及びホーチミン支店設立。
クアラルンプールにて、人材紹介会社「CLCリクルート」設立。
2011年
ベトナムの週刊誌『アットサイゴン』のマネージメント業を開始。
シンガポールにて、日本の文化及び情報をアジアの人々に伝える目的で、テレビ局『J FOOD&CULTURE TV』を設立。シンガポール邦人コミュニティに根ざす非営利FMラジオ局として『FM96.3SMILE WAVE』放送開始。
2012年
インドにて、海外引っ越し事業の営業開始(予定)。
こうして改めてふり返ってみて、アジアの8か国で広く展開し、なによりも長く継続できてきたことには明確な理由があることを再認識した。
それは次の10項目だ。
1 慌てず段階を踏んでビジネスを展開してきた。
2 日本のビジネスモデルを各国の仕様にアレンジしてきた。
3 タコ足のように多角化を進めてきた。
4 常に先を読む努力を怠らなかった。
5 資本力のなさを逆手にとった。
6 偏見を持たずに多文化を受け入れてきた。
7 ビジネスパートナーを信頼した(これは途中で気づいたことだが)。
8 女性を積極的に登用してきた。
9 ニッチを常に意識してきた。
10 常に退路を断ち、覚悟を持って努力を重ねた。
以上だ。
この章では、それぞれについて、具体的にお話ししたい。
事業展開は慌てず、段階を踏む
アジアビジネス成功の秘訣 その1
前述のクラウンライン・グループの歴史を見ていただくとわかると思うが、私の会社は、慌てず、段階を踏んで成長をしてきた。
そこには、ある一定のルールがある。
まず、海外引っ越し業務を始め、その地域に倉庫などの環境を整え、出版物を主としたメディア戦略の展開、というプロセスで事業を展開しているのだ。
そのパッケージを、まずシンガポールで行い、マレーシア、インドネシア、タイ、中国、ベトナムと展開してきた。
すでに書いた通り、生活情報誌を始めたのは、近所に住み家族ぐるみでお付き合いをしていた日本人家族の奥さんの自殺がきっかけだった。慣れない海外生活で悩みやストレスを抱えた結果の不幸な出来事だった。
体験したことがある人には理解できると思うが、海外生活は孤独との闘いだ。自分が抱えている不安を相談できる相手がいない、病気になったときにどうしていいかわからない・・・・・など、日常生活で悩む人は実に多い。何か事件が起きたときよりも、ごく日常の不安で、人はきりきりと苦しめられていく。
だから、海外引っ越し業とは直接関係ないけれど、生活情報誌を作ったわけだ。クラウンライン・グループの生活情報誌『ハロー』シリーズは、病院や学校のような現実的な生活情報だけではなく、現地在住の日本人コミュニティの紹介なども積極的に行っている。
ビジネスというのは、顧客を開拓して「買ってください」と営業するばかりではいけない。大局的に世のなかを見る必要がある。そして、今何が必要なのか?社会では何が求められているのか?を見極め、多くの人が「欲しい!」と願う質の高いサービスを提供することが重要なのだ。収益は後からついてくる。極端なことをいえば、誰もが「どうか分けてください」と言ってくるようなサービスを提供しなくてはいけない。
そして、一見引っ越し業とは無関係に感じられる、生活情報誌の発行は、顧客に活用してもらい、親しみを持たれ、会社の信用となり、本業へと還された。
かつて、テレビ朝日系の『モーニングショー』から『スーパーモーニング』にかけての人気コーナーに『宮尾すすむのああ日本の社長』があった。日本が好景気に沸いた1979年から20年にもわたって続いていた。そのちょうどバブルの時代に海外特番に出演したことがある。
あれば、宮尾すすむさんのキャラクターあってこそのコーナー。宮尾さんはゲストの社長の、自宅の冷蔵庫を平気で開けてしまう。すると、そこには高価なマスクメロンがあったりする。
「あっ、やっぱりありました。マスクメロンでございます!」そう言って目をくりくりさせる。実に楽しかった。
あの番組に出演して何年も経ってから、日本に帰ったときに、宮尾さんと番組のプロデューサーに会い、驚くべき事実を聞いた。
番組に出演した社長のかなり多くが、その後倒産し、行方不明になったというのだ。
自殺した人も少なくはないらしい。
これは想像の域を出ないが、多くの経営者は、先を急いだのではないだろうか。先を急いで、無謀な勝負を仕掛けたのではないだろうか。
創業間もない時期に社員たちに造反され、お金を奪われた体験を持つせいか、私は慎重さを心がけてきた。勝つよりも負けない、奪うよりも奪われない闘いをしてきた。
それこそが、30年以上も会社が継続できた理由の一つだという気がしている。
日本のビジネスモデルをアジア仕様に変換
アジアビジネス成功の秘訣 その2
私が海外引っ越し業をスタートした1980年には、日本の宅配ビジネスは成熟しつつあった。成功のスタイルがある程度確立していた。私はそれをアジア各国で活用し、成果を挙げてきた。
なぜ、私がアジア全域のビジネスで成果を挙げることができているか。
それには、スタートがシンガポールだったことが大きい。
シンガポールの面積は約710平方キロメートル。東京23区の面積とさほど変わらない。人口は500万人強。この狭い日本ですら、面積は約37万平方キロメートルある。人口は約1億2800万人だ。これでわかっていただけると思うが、シンガポールは実に狭い。箱庭のような国だ。
狭いことには思わぬ利点が多い。まず、外国人の私でも国全体の把握に時間がかからなかった。
そして、非常に統制がとれている。法律が隅々まで行きわたっている“ルールの国”なのだ。ルールにきちんと従えば、国が守ってくれる。だから、ビジネスもルールにのっとって正攻法で行えば、ある程度は成果が見えてくる。予期せぬ出来事は比較的少ないものだ。
この国は、暮らしやすいし、ビジネスもやりやすい。
個人としては、まず税金が少ない。地方税がなく、どんなに多い人でも個人の所得税は最高20%しか徴収されない(2011年11月現在。日本は所得税だけでも最高400%)。
さらに法人税は17%に定められている。
また、国が40%弱の積立金を強制している。しかし、実は、この制度はありがたい。
1か月の収入が日本円で20万円の人の場合、積立金は8万円弱だ。ただし、半分は公社負担なので、個人の給与からは4万円弱しか引かれず、16万円強は手に入る。でも、毎月8万円弱は積み立てられていく。借金で自己破産しても、この積立金は国によって守られる。そして、55歳を迎えるときちんと返してくれる。この時点で、個人差はあるものの、数千万円から億単位の積み立てになっている。
ちなみに、シンガポールでは55歳を過ぎて人生で失敗をする男が多い。積立金が戻ってきていきなり経済的に豊かになるからだ。それまでに見たことがないような大金を突然持つと、人生を誤ってしまう。ギャンブルにはまったり、女性にはまったりする。この世代の男を集中的に狙ってカモにする女性も後を絶たない。しかし、こういう理由で人生をダメにするのは、あくまでも本人のせいなので、しかたがない。
そして、日本と比べて開発途上の分野が多いことも、日本人がここでビジネスを行うのに有利だ。日本でうまくいっているビジネスモデルをスライドして、ルールにのっとったシンガポール社会の仕様にアレンジすれば、成功率が高まるのだ。
だから、すでに成熟しつつあった引っ越しや宅配業務をシンガポールに移行すれば、成果が見込めたわけだ。
同じことは、他業種にも応用できる。日本で成功しているビジネスモデルを、シンガポールに移行して多少工夫を加えて行う。その後、中国仕様、インドネシア仕様にアレンジする。この法則で、広くアジア各国に展開していけばいいのだ。
タコ足のように多角化を進めろ
アジアビジネス成功の秘訣 その3
「アジアでの展開はタコ足のようなもんやな」
ときどき感じる。
私の場合、タコの本体がシンガポールだとしよう。その本体が充実したら、外に向かってニョキニョキと足を伸ばしていった。そこでビジネスチャンスを得ると、また別の方向へニョキニョキと足を伸ばしていく。その結果が、前述のクラウンライン・グループのアジア展開だった。
そして、大きな間違いを起こさなければ、展開は加速していく。市場の情報は足し算で増えるのではなく、2乗、3乗と、累乗していくからだ。
ややえげつない喩えだが、アジアでのビジネス展開は、生物の食物連鎖にも似ている。大は小を食うことによって見えていくのだ。新規の国、新規のエリアに展開すれば、当然、そこにある競合企業との闘いになる。そして勝利を収めると、「うちの会社をまるごと買ってほしい」と言われることも多い。すると、会社も、人材も、そこにある情報も、全部手に入るのだ。
こうして引っ越し業を新規のマーケットへ進出させると、そこでまた倉庫はもちろん、生活情報サービスなどをタコ足のように展開するのだ。
常に先を読む努力を怠らない
アジアビジネス成功の秘訣 その4
広くアジアに展開すればそれだけ、国境を越えた情報が手に入る。シンガポールにいても、マレーシアやインドネシアや中国の情報はリアルタイムで入ってくる。ましてや引っ越し業だ。海の向こうから引っ越してくる人から生きた情報も手に入る。
引っ越し業というのは、その性質上、景気の変動が本当によくわかる。人がごそっと動き始める理由は、好景気か不況か、必ずそのどちらかだ。
通常は、景気の悪い地域から、いい地域へと人は動いていく。それを敏感にキャッチして、ビジネスの方向性を決めていけばいい。
そんななかで私が一つの目安にしているのが華僑の動きだ。彼らが大量に動くときは必ず何かがある。
タイに住む中国人が家財をカナダとアメリカへいっせいに運んだ時期があった。それから1年もしないうちに、タイでクーデターが起きた。
1990年前後からは、香港に住む中国人がいっせいに引っ越しを始めた。もちろん、香港の中国返還を見越しての民族移動だ。
華僑は、地球全体を見て生きている。だから、子どもが3人いたら、一人はアメリカ、一人はイギリス、一人は日本に留学させる。日本の安土桃山時代、信濃上田の武将、真田昌幸(さなだまさゆき)が関ヶ原の合戦の際、長男の信之(のぶゆき)を東軍の徳川家康に、次男の幸村(ゆきむら)を西軍の石田三成につけて、東西どちらが勝利しても真田家を存続させようとした事例にも似ている。
シンガポールの経済の危機でいえば、1985年に石油価格の下落で近隣の国が不況に陥ったその煽(あお)りで、1997年にはアジア通貨危機によって、2003年にはイラク戦争とSARS (サーズ:新型肺炎)によって、大きなダメージを受けている。こうしたときにも、ごそっと人が動く。日本企業は、経費節減のために現地駐在員を一気に引き上げるからだ。不謹慎だが、こういう負の状況のときも引っ越し業では稼がせていただいた。
アジアには開発途上国も多いので、戦争や暴動も起きる。すると、日本企業は短期的か長期的かはともかく、いずれにしてもそこから撤退する。そういうときも私の会社の出番だ。そして、戦争や暴動が終わって現地に人が戻るときもまた仕事が発生する。
こうして、時代の変化のたびにビジネスをやらせていただいた。
資本力がないことを逆手にとれ
アジアビジネス成功の秘訣 その5
学歴がないだけではなく、金がなかったことが功を奏した体験は多い。
海外進出に限らず新しいマーケットを開拓する場合は、ふつうは調査会社との協力のもと、大規模な市場調査を行う。しかし、私のようにまさしく裸一貫で成り上がってきた人間には調査にコストなどかけられない。調査会社に払うような余分な金など持ち合わせていないからだ。
では、どうするか?
そこには、いくつかのポイントがある。
まず、クラウンライン・グループの顧客は日本人なので、日本人小中学校の生徒数、日本人会の会員数、商工会議所の会員数を調べる。これはさほど難しくない。そこからの係数で、おおよそのマーケット規模は知ることができた。さらに、日本食レストランと日本人ラウンジの数と客席数がわかれば、マーケット規模はほぼ把握できた。ただし、今では、外国人も日本食を積極的に食べるので、少し複雑な計算式にはなっている。
また、その地域に進出するかどうかのジャッジは、「カルフール」と「イケア」を参考にすればいい。
カルフールは、1959年にフランスで創業した世界第2位の売上を誇るスーパーマーケットだ。世界で初めてハイパーマーケットの概念をつくった。カルフールは、EU諸国はもちろん、アフリカ、南米、中近東、そしてシンガポールにも進出している。
イケアは、1943年にスウェーデンで創業した大手家具店だ。世界の40か国近くで約300店舗を展開している。
この両社とも、新規出店の際は、念入りな市場調査を行っている。つまり、この両社の店舗がある土地にはビジネスチャンスがあると判断していい。
私は、どちらか一つがあればその地域は前向きに検討し、両社ともあれば迷わず進出している。
こうした知恵は、“持たない”、つまり資本力がないからこそ培われたものだ。
偏見を持たずに多文化を認める
アジアビジネス成功の秘訣 その6
アジア各国でビジネス展開する時、日本人はどうしても上から目線で接してしまう傾向がある。これは大きな間違いだ。その国に入ってビジネスをさせてもらうのだから、謙虚でなければいけない。
加えて、その国の情勢、国民性を理解する必要がある。これは一筋縄ではいかない。説明を受け、知識としては理解できても、その土地だからこその原理原則が身体に染みついていないと、個々の場面で判断を誤るものだ。
だから、その土地へ行ったら、その土地の流儀に従うようにしている。
「郷に入っては郷に従え」という言葉の通りだ。
例えば、インドの人たちは手づかみで食事をする。日本人には、どう考えても不潔にしか感じられない。こういう習慣を日本ではよく「異文化」という言い方をする。異なる国の異なる文化というわけだ。この異文化という言葉に、私は上からの目線を感じている。自分の国が正しくて、ほかは異質なものだというニュアンスが含まれているように思える。
しかし、世界に100の地域があれば100種類の文化がある。「日本とその他」ではなく、全部違うのだ。これを私は「多文化」と解釈している。
多文化だと認識すると、どこへ行っても、その土地の文化を受け入れる気持ちになれるものだ。インドへ行ったら、手づかみで食事をしてみようと思う。インドの人の気持ちを理解することまではできなくても、「こんなふうに考えているのかもしれない」と、イメージするくらいはできるかもしれない。
また、開発途上国でタクシーに乗ると、よくわざと遠回りをされる。ドライバーが客から高い料金を取るためだ。かつては、私も頭に来た。よく怒ったものだった。しかし今では、そういう国では、時間が許すならば素直に遠回りさせるようになった。稼げるチャンスに出会ったら稼ごうとするのが、その国の文化だととらえれば、少しは寛大な気持ちにもなれるというものだ。
シンガポールでも、最初は戸惑うことが多かった。現地採用の社員が、時間を守らない。約束を守らない。しかも、まったく悪気がないのだ。だから、叱っても、きょとんとしている。最初は腹が立った。しかし、それもまた文化なのだ。
世界全体で見ると、もしかしたら時間厳守の習慣がある国のほうが少ないかもしれない。アメリカの都市部ですら時間厳守の習慣はない。時刻表通りに電車が来る日本のほうが珍しいのだ。
こうして「多文化」という概念に気づき、受け入れると、気持ちが楽になり、おおらかになった。
ビジネスパートナーを信頼する
アジアビジネス成功の秘訣 その7
広くアジアに展開していく過程で、私はある程度開き直った。ビジネスのパイが大きくなれば、そのすべてを細部まで把握しコントロールすることは不可能だ。
だから、アジア各国では、その土地で頼できる人間を探し、コミュニケーションをはかり、「信頼するに足りる!」とジャッジできた時点で、その人物にすべてを任せてしまうことにした。
一度任せたら、細かいことは言わない。数字も、要所をチェックするだけにとどめる。
例えば、日本でいう接待交際費に該当するような細かい経費の支出にはできるだけ意見ははさまない。これは、シンガポールで会社を興した当初のオレ様時代に人望を失い、痛い目に遭った経験が生きている。あのときは、社員の行動から経費の使い方まで細かくチェックをして、精神的に追い詰めてしまった。その結果、造反されたのだ。自分がやった行いがすべて自分に返ってきた。
クラウンライン・グループのシンガポール以外の国の法人では基本ルールがある。
トータルの利益の30%はそこの責任者の取り分。30%は私。残りの40%は会社にプールする。今はどの地域も順調に売上を伸ばしているが、何か問題が起きたとき、行き詰まったときは、貯蓄したその40%のお金を使う。
各国の経営者の取り分30%の使い道については、すべて任せている。その枠内で、従業員を何人雇用しようが、どういう割合で分配しようが、極端な話だが経営者が独り占めしようが、自由だ。任せている。
このルールで、どの国でも概ねうまくいっている。
女性を積極的に登用しろ
アジアビジネス成功の秘訣その8
各国の経営者、つまり私のパートナーたちはほとんどが女性だ。最初から女性を選んだというわけではない。ただ、今の時代は女性のほうが頑張ってくれると感じている。
自分が男性なので、その心境はよく理解できるのだが、男にはつまらないプライドがある。いわゆる、見栄だ。いらないところにお金を使う習性は、どの国の男も共通して持つ性質だ。
その点、多くの女性は実に現実的で、堅実だ。無駄を排し、目指すべき方向に向かってきちんとビジネスを推し進めてくれる。
また、男性と比べると、概して、お金に対する欲が少ない。より正確にいうと、女性の欲望に限度がある気がしている。自分に歯止めをかけられるので、男性と組むよりは裏切られるリスクが小さいと思っている。欲が強いのはトップの私だけでいい。
日本国内でビジネスをする場合も同じではないかと思うが、これからは、より女性と上手にパートナーシップを結ぶべきだと思う。女性スタッフに責任ある仕事を任せることが会社を発展させると思う。
クラウンライン・グループについていえば、今思えば、離婚歴のある女性社員が活躍してくれた。男性に頼らず、何よりも退路を断った状況で働いてくれるからだ。
それは、海の向こうでより顕著だ。夫と別れ、日本と別れ、二重に退路を断っているからである。しかも、男と違って、女性は過去を引きずらずに、きっぱりと自分をリセットして新しい環境に臨んでくれる。腹の据わり方がいい。
だから、特に海外では、女性を積極的に採用している。本当に、彼女たちはよく働いてくれる。
退路を断つということは、ビジネスを行ううえでの大きな強みだ。
ニッチを狙う
アジアビジネス成功の秘訣 その9
これまでにもくり返し書いてきたが、徹底してニッチを狙うことこそが明らかに私のビジネスを、ひいては私の人生を切り拓いてきた。それははっきりと感じている。
私の場合はできる限り知恵を働かせてパイオニアを目指した。つまり、徹底的に競合相手が少ない、未成熟の、勝つ可能性の高い分野を探しに探して勝負をしたのだ。
1980年代のシンガポールという開発途上の場所で、海外引っ越しという未成熟分野で起業したことは、ニッチゆえに独自なもので、他の追随を許さなかった。シンガポールにいながら、そこにいるごく少数の日本人を顧客としてイメージしたわけだから、二重、三重にニッチだったといっていいだろう。
ご承知の通り、日本国内の引っ越し業は、ドア・トゥ・ドアが常識だ。しかし、実は1980年代のシンガポールでは、まだそんな会社はなかった。現地在住日本人向けの情報誌もなかった。日本で当たり前のことが、向こうでは前例がない。そういうものを見つけては次々と持っていって、ビジネス化したわけだ。
今後もさまざまな可能性がある。現地に住む日本人のためだけでなく、現地人にも今、日本で流行っている日本の番組を放送する。それから、現地日本人のための結婚情報、つまり男女のマッチングサービスを行う。また、ネット配信によって日本の新刊書を読めるようにする・・・・・・。新しい発想は尽きない。
これらはすべて、日本以外のアジアだからこそだ。日本のようにあらゆる産業が成熟していると、未開拓といえる分野がものすごく限られてしまう。しかし、シンガポールやほかのアジア諸国ならば、誰も手をつけていない分野がまだまだたくさんある。
そういった意味でも、これからの若い人たちには特に、勝負の場として、アジアを意識してほしい。
退路を断つ
アジアビジネス成功の秘訣 その10
退路を断つこともまたくり返し書いてきたことだ。これは、ビジネスのみならず、人生の肝になることだと私は思っている。
先進国の日本では、多くの若い人は「安定」を最優先に仕事を選ぶ。やりたい分野で勝負しようとしたり、自分の力でビジネスを展開したりという意識は希薄だ。それは親の世代にも責任はある。親は子どもが公務員や上場企業の社員になることを望み、言い聞かせて育ててきた。
しかし、不況が延々と続く日本で、安定している職場などもはやほとんどない。不況は、今や“日常”となりつつある。これからは間違いなく、安定して働ける場所はもっと少なくなっていくだろう。
それならば、勝負してみないか?
人生はたった一度しかない。
だったら、勝負してみない手はないだろう。
そして、その選択肢の一つとして、日本以外のアジアを検討してみるべきだ。
何度も言うが、広いアジアには、勝負できる分野、勝負できるエリア、勝負できる手段が、日本よりも多いからである。
こういう考えに至ったのは、私が子どもの頃に赤貧を体験したからだと思っている。自分の力で生きざるを得なかったからだと思っている。
ちょっとまともな大人ならば、仕事を重ねていく過程で、そして生きていく過程で、退路を断たなくては大きな成果が挙がらないという原理原則を知る。しかし、その理屈を頭で理解しても、退路は断てないものだ。
怖いからである。
しかし、私の場合は、不幸中の幸いで、貧しさゆえ、子どもの頃から退路を断たざるを得なかった。退路を与えられなかったといってもいいかもしれない。かつてはそれがハンディキャップであったわけだが、大人になりビジネスを始めてからは、ずっとアドバンテージになっていると理解している。
何度も言うが、人は退路を断ったとき、とてつもない力を発揮する。
続き「第7章」(#10)はこちらからどうぞ

『アジアで負けない三流主義』
ゲーテビジネス新書 幻冬舎

著者:森 幹雄(もり みきお)
クラウンライン・グループ社主・CEO
海外日系新聞放送協会副会長
アジア経営者連合会理事
シンガポール日本人会理事
1953年京都府生まれ。工業高校卒業後、日立製作所入社。退社後、アメリカを経て、単身シンガポールへ渡る。外資系引っ越し会社に3年間勤務後、日本人による日本人のための海外引っ越し専門会社クラウンラインを設立。今では11か国21都市に進出する。本業以外にも出版・情報サービス、イベント企画などを展開中。
アジアビジネス実践塾 www.sg-biz.com
✉:mori@comm.com.sg まで、お気軽にご連絡を!