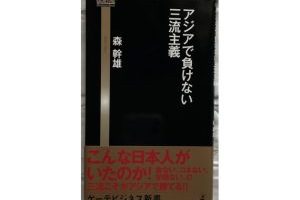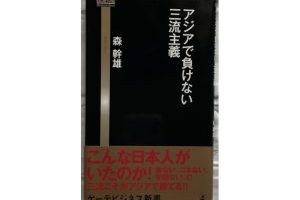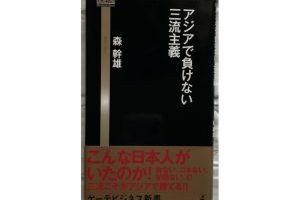2025.04.28
「金なし、コネなし、学歴なし」⸺“三流”だからこそ勝てたアジアビジネスのリアルを描いた一冊、『アジアで負けない三流主義』。引き続きお楽しみください。
前回#5の内容を読みたい方はこちら!
#1から読みたい方はこちら!
第3章 近道せず王道を行く
一度の不採用であきらめるな
シンガポールの引っ越し会社合格
「はじめに」にも書いた通り、アメリカでの生活はVISAの問題で、1年半ほどで終了することになった。
このときは中途半端なアメリカ滞在になったように感じて、悔しい思いもあったが、後からふり返ってみれば、アジアでビジネスをするための貴重な助走期間だったと感じている。
必死にやりさえすれば、世の中には無駄なことなど何一つない。
帰国して就いたのは、インド料理店の雇われ支配人の仕事だった。朝から深夜まで、ビルの地下にある店で働きながら、「もう一度海外へ出たい!」という気持ちを膨らませていた。それで毎日『ジャパン・タイムズ』の求人広告を目を皿のようにしてチェックしていた。その時に発見したのが「MOVING」という求人だったのだ。
SINGAPOREでアメリカ系の引っ越し会社が現地スタッフを募集していたわけだが、実は最初は映画の仕事だと思った。アメリカではハリウッドの近くに住んでいたこともあって、これはすごいぞ。スターに会えるぞ。大女優と恋におちたら・・・・・・なんて妄想を膨らましたのだが、要するに「MOVIE」と勘違いしたのだ。
今から思うと、この頃の私の英語力は、相当あやしかったのかもしれない。そして、すべてを自分の都合のいいように考える癖は、今も変わってはいない。
そもそもはオーストラリアに渡ろうと思っていた。ただ、当時のオーストラリアは白蒙主義が残っており、VISAも厳しく、ならば同じ元英国植民地で、オーストラリアに行ける情報を得られるかもという思いでシンガポールを選んだ。
このシンガポールの引っ越し専門会社の面接試験を受けて合格したことはすでに書いたが、実は一度「不採用」になっている。というのも、面接の後、待てど暮らせど連絡が来ないので、しびれをきらして電話をした。
「面接した当日に不採用通知を送付しています」冷淡に言われたのだ。
「そもそも君が採用になるわけがないだろ」そこまで言われた。
ところが、さらに3か月後、その会社のアメリカ人オーナーが日本に来た時に、もう一度面接がしたいという旨の連絡があった。
「君は、本当に海外で仕事をする気があるのか?」
英語の試験を受けさせられ、さんざん意地の悪い質問をぶつけられたうえにさらにふざけたことを聞いてくる。堪忍袋の緒が切れた。
「あなた、よくそんな質問ができますね?そもそもこの会社の面接試験を最初に受けたのは3か月以上も前。そのときは採用・不採用の通知すらよこさなかったじゃないですか!しびれをきらしてこちらから電話をすると、“不採用”だという。それでも、今回また英語の試験と面接を受けにやってきているんです。海外で働きたいに決まっているでしょう!」と一気にまくしたてた。
それで採用が決まった。
「私が知る日本人は感情をほとんど表に出さないし、ディベートもできない。しかし、君は違う」それが採用の理由だった。
これだけのプロセスを経て、シンガポールに渡ったのである。
「実は、君は補欠の補欠の更に補欠だったんだ。本当に採用したかった応募者が次々と辞退したから君に行ってもらうことになった」出発前に日本オフィスのスタッフに言われた事情も、アメリカ人オーナーが「君は本気なのか?」と質問した理由も、後でわかった。
3か月前に採用した人は研修中に渡航を家族に反対されて退社。二人目は研修中に病気になり退社。3人目は二股をかけていた他社に入社。それで私にお鉢が回ってきたのだ。
「オレは強運だ!」はっきりと感じた。
「この野郎、オレなしではどうにもならない会社にしてやる!」
そう心に誓ったのは、こうした事情を知ったからでもある。
最初は無我夢中で働け
シンガポールのアメリカ系引っ越し会社体験
1977年8月、私は初めてシンガポールの土を踏んだ。
「いきそうな国だな」
マレーシア連邦から独立して10年強。この国は活気に満ちていた。
違和感はまったくなかった。シンガポールはLAに印象が似ていたのだ。アメリカ人もいれば、中国人もいるし、インド人もいる。どの国から来た人にもバイタリティを感じた。
「この国で勝負しょう!」という意気込みが誰の表情からも感じられたのだ。
私は働いた。働いて働いて働きまくった。
「今度こそ、なにがなんでも成功する!」強く心に誓っていた。
当時の月給は1,000ドル。住宅手当のような福利厚生などない。オーストラリア人の家に居候をして、その家の掃除をし、毎日朝食を作って家賃を無料にしてくれた。
1日に最低6件の飛び込み営業をノルマとして自分に課していた。移動はHONDAのスーパーカブだ。スコールを浴び、バスやトラックの排気ガスをもろに浴び、ワイシャツは午後には真っ黒になった。
そして、約1年で努力は報われる。
営業実績が評価されて、大きな家に住める収入を得られるようになった。乗り物もスーパーカブから自動車へ“出世”した。
勤務して3年目には「地域統括責任者兼シンガポール副支店長」になった。
ただ、その頃から、勤務していた会社と自分が理想とするスタイルとの間にギャップを感じ始めてもいた。日本人の顧客に対しては、引っ越しに特化せずに、そこから派生するもっと親身なサービスが必要ではないか。そう考えるようになったのである。
それが次のステージへと進むきっかけになった。
見た目は大切。体裁を整えろ
クラウンライン創業
独立し、海外専門の引っ越し会社、クラウンラインを興したのは1980年3月。27歳と1か月のときだった。
最初のオフィスは、日本航空、東京銀行(現、三菱UFJ銀行)、三井物産、丸紅・・・・・など日本の超一流企業が入っているビルに構えた。東京でいえば丸の内にある丸ビルのようなところである。面積は45平方メートルだ。
なぜ、そこに事務所を構えたか、それは「看板と信用」が欲しかったからだ。
世の中、勝負どころではったりを利かせることはものすごく大切だ。27歳の若造が分相応に街のはずれに小さなオフィスからスタートしたら、大きな仕事などできない。多くの人は名刺に一等地の住所が印刷されていることでこちらを信頼するのだ。実際、名刺に住所を大きく太く記載した。

創業間もない頃、作業現場にて(右が筆者)
引っ越し業は、顧客の大切な財産をまるまる預かる仕事だ。特に体裁が重要だ。
とはいえ、保証金と家賃は恐ろしく高かった。事務所を借り、電話を引いたら、デスクや椅子を買う金も残らなかった。ないものはしかたがない。フロアに電話帳を積み、そこに電話を置いて、床にゴザを敷いてベタッと座って、仕事をしていた。ときどき会社に来ようとする顧客もいたが、そんな事務所だとばれないように、あらゆる理由をこしらえてかわした。それでも訪れた客とは、地下にあるコーヒーショップで会った。
オフィス同様、自分の体裁も整えた。まずは髭をはやした。そして、高価なスーツを着て高価なバッグを持つようにした。別におしゃれをしたかったわけではない。少しでも歳が上に見られるために必要だと判断したからだ。ほとんどの人は最初は見た目で人をジャッジするものだ。
どこにお金を使い、どこにお金を使わないか。それは厳しく見極めなければいけない。
こうして会社は動き始めた。
後発は手段を選ぶな
ルール無用の営業展開
何でもやった。
無理だと言われれば言われるほど燃えた。
小さな会社が大きな会社に対抗するには、どんなことにも躊躇してはいけない。仕事は、待っていてはダメだ。自分から取りに行かなくてはいけない。
すでに荷造りがすんでいる仕事を横から奪ったこともあった。
ある日、日本へ帰る家族があるという情報をつかみ、訪ねると、すでに荷物は整理されていた。段ボールを見ると、◯通のロゴマーク。そこであきらめて帰るのが普通だろう。しかし、私は違う。そこから交渉が始まる。料金、アフターケア・・・・・・その他さまざまな条件を提示して、その家の奥さんのかたくなな意思をほどいていった。
しかし、「それでも・・・・・・」と難色を示した。◯通に断りづらいというのだ。もっともだ。そこで、私が代わりに◯通に断りの電話を入れた。
「奥さんはうちの会社を使って引っ越すと言っていますので、作業を進めています」
慌てて◯通がやってきたが、作業は大方すんでしまっていた。◯通の段ボール箱に入れたまま、うちが運んでしまったのだ。
「私はおたくでいいけれど、夫がなんと言うか・・・・・」引っ越すという家を訪ねると、そう言われることも多い。
もちろんあきらめない。主人に直接交渉する。電話でダメならば、職場を訪ねる。
主人は当然忙しい。なかなか相手をしてはくれない。しかし、どんな人間でもトイレへは行く。3、4時間に一度は小便はしたくなる。だから、トイレの前で待ち伏せをした。したくてもぞもぞしている相手に直接交渉して仕事を確保したことは何度もある。
ルール無用、メチャクチャな営業だったが、こうして仕事を増やし、会社はどんどん大きくなっていった。
人がやらないことを最初にやれ
『ハローシンガポール』創刊
引っ越し業からはさまざまなビジネスが広がった。
その主なものの一つが情報誌の発行だ。それが、日本のNTTが発行している『ハローページ』をひな形にした『ハローシンガポール』だ。不動産情報、接待用のレストラン情報、就職情報・・・・・などさまざまな生活情報を満載した電話帳だ。
これが大ヒットした。
日本からシンガポールへ、無事引っ越しをしても、その後にはさまざまな問題がある。
子どもの学校や幼稚園はどうするのか?病院はどこにあるのか?日本人のコミュニティはあるのか?などだ。
「ハローシンガポール」出版のきっかけは、ある日本人駐在員の奥さんの自殺だった。彼女の家が近所だったこともあり、家族ぐるみのお付き合いもしていた。
死因はノイローゼ。なぜ心の闇に気づいてあげられなかったのか。猛烈に悔やまれた。
1970年代、1980年代は日系の製造メーカーの進出が盛んで、多くの日本人がシンガポールに駐在していた。しかし、その数に対して、生活情報が追いつかないのが実情だった。
例えば、日本人とシンガポールのマレー人との間には宗教上の慣習の違いがある。マレー系の子どもに対して「かわいいわねえ」と頭をさするのはタブーだ。その子の親から猛烈な抗議を受けることになる。
こういうことが日常的に次々と起こると、どうしていいかわからなくなってくる。日本にいれば、身内や友人に悩みを打ち明けられるが、そういうわけにもいかない。繊細な心の持ち主だと耐えられなくなってくる。自殺した奥さんも、そんな海外生活になじめなかったのだ。
そこで、シンガポール在住の主婦や出版業界出身の方々からボランティアを募り、『ハローシンガポール』を創刊したのだ。
とはいっても最初はA4サイズの紙1枚からだった。中身も誤植だらけで、散々な仕上がりだった。しかし、あっという間に雑誌レベルに成長した。
この媒体は、今では、香港、北京、上海、華北、タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム・・・・・・などでも発行した。
人がやっていない事をやるのは、ビジネスの鉄則だ。
ビジネスは多角的に
異業種へのビジネス展開
ほかにも、さまざまなビジネスを行っている。
引っ越し業のほかで、最初に手掛けたのは、不動産の仲介だった。
不動産業は、引っ越し業とは切っても切り離せない関係。引っ越しと不動産はセット。だったら、自分でもやってしまおうということだった。
当時、不思議なことに、シンガポールでは引っ越し業と不動産業を同時にやっている企業はなかった。このあたりが、日本と比べてはるかにビジネスチャンスが多い理由だ。
引っ越しを請け負った顧客に不動産を仲介するだけで手数料を得ることができるので、このビジネスはうまくいかないはずがない。
そして、あるとき気がついた。ビジネスは、いつどこでどんなトラブルが待っているかわからない。一つが行き詰まっても生き延びられるように、多角的な展開は絶対に必要だ、と。
そこで考えたのが、郵便によるメーリングサービスだ。
広告活動といえば、日系の新聞に折り込み広告を挟むか、ダイレクトメールという時代である。そこで、メーリングサービスを始めたのだ。
このビジネスの需要は多く、一時期は非常にうまくいっていたが、その後裕福な日本人宅の強盗が増え、日本人会の名簿の管理が厳しくなり、やめざるを得なくなった。
そのあとに手掛けたのが、日本人家庭への健康食品やサプリメントの販売だったが、これは引っ越しの顧客にサンプルをサービスする域を出なかった。
1980年代の10年間は、次々にビジネスのアイディアを実現させていった。
なかには、コンピューター画面の見すぎによる疲れを軽減させるフィルターの販売、人エフカヒレの開発、カイワレ大根やアルファルファや芽紫蘇(めじそ)の水耕栽培と卸しなども手掛けた。あるものは鳴かず飛ばず、あるものはある程度儲かりもしたが、引っ越し業のように長期的に続くビジネスとはなかなか出合えなかった。
後発は常に知恵で勝負しろ
日本食レストランと地ビール
日本食レストランのビジネスを手掛けたこともあった。
レストランを持つことには、長い間憧れの気持ちを抱いていた。
それは、やはり、子どもの頃の好きなだけ食べられなかった経験があったからだ。
「おいしいものが食べたい!」「お腹いっぱい食べたい!」10歳に満たない時期に味わった赤貧体験からの渇望は、何不自由なく食べられるようになり大人になってなお身体の中に残っている。また、アメリカから帰国して働いていたインド料理店での体験も生かせるのではないかという目算もあった。
条件にも恵まれているように見えた。
本業が引っ越し業ゆえ、すでに一等地に倉庫を持っていた。だから、食材の保管場所には困らない。トラックとそれを運転するスタッフもいた。また、仕事関係の人たちへの接待に自分の店を使うことで、ビジネスに好循環を生むこともできるとも考えた。
その頃のシンガポールにあった日本食レストランは2系統。若いうちにシンガポールに移り住み修業時代を経て独立したオーナー店と、大手日本食レストランの海外支店だ。
後発であり、他業種からの参入というハンディキャップを埋めるには何をすればいいか。私は考えに考え、貴重な日本酒を多数そろえる店を開くことにした。さっそく日本に出向き、北海道から九州の酒蔵をまわって話をつけ、日本にいてもなかなか飲めない貴重な吟醸酒が200種類以上そろう店「酒蔵(くらま)」をオープン。日本で各酒蔵をまわった際は、それぞれの酒の最もおいしい飲み方をこと細かく教わった。
日本酒の輸送にも、引っ越し業のネットワークが役立った。高品質の吟醸酒をその風味を保ったまま運べる温度5度設定のコンテナ船を確保できたのだ。
店は大変な評判になった。
しかし、それだけでは我慢できないのが私の性分だ。きき酒師の資格も取得。やがて、自分でも酒造りを始めた。
自製したのはビールだ。日本ではまだ解禁前だったが、シンガポールでは認められていた。さっそく、カリフォルニアから醸造士を呼び、地ビールの工場とそれを飲ませるビアホールをオープンした。「オランウータンビール」地ビールには、そう命名した。
私の苗字は「森」。オランウータンにはマレー語で「森の人」という意味がある。それで「オランウータンビール」と名付けたのだ。
ただし、既存の大手ビール会社との軋轢(あつれき)、シンガポール政府とのライセンス契約の交渉には、相当のエネルギーと時間を費やした。そして、当然のことながらコストがかさむ。
店や工場は引っ越し業とは別法人にしていた。やがて、業績の悪化とともに、ビール醸造関係の取締役たちとの間に意見のギャップが生じ、それがどんどん大きくなっていった。そして、最終的には撤退に至った。
このとき、他人と一緒に会社を経営する難しさを痛感した。私の場合は自分自身ですべてをコントロールできるビジネスが向いていると感じている。
さて、日本食レストランの「酒蔵」のほうも、最終的にはクローズとなった。店が入居していたビルから立ち退きの憂き目にあったり、社員のトラブルもあって残念ながら涙を飲んだのだ。
しかし、今なお、日本食レストランを手掛けるプランは持ち続けている。2012年には抹茶カフェを日本人パートナーと一緒にシンガポールとタイにオープンした。
近道をしない
シンガポールでのビジネスの鉄則
当初、オーストラリアに渡ろうとし、軽い気持ちで訪れたシンガポールだったが、ここを選んで正解、つくづくラッキーだったと今では思う。
シンガポールは東京23区とほぼ同じ面積の小国だ。国ができて60年と歴史も浅い。
もちろん資源もなく、人口も少ないからマーケットもない。ゆえに、政府は常に危機感を持って、国の舵取りをしている。新しいものもどんどん取り入れる。法律も完璧に整っている。
ゴミーつ落とすだけで厳しく罰せられるのは有名な話だ。
そんな国でビジネスを行うには、王道を行く他はない。アジアでよく聞く賄賂なんて、シンガポールでは、そもそも効果がない。しかもばれたら厳罰。要するに近道がないのである。
もし、私がシンガポールではなく、当時、東南アジアのなかで頭一つ抜き出ていたフイリピンでビジネスを行っていたら、おそらくあのマルコス元大統領やイメルダ夫人や政府の面々とうまく付き合い、日本のODAを取り仕切る顔役になっていたかもしれない。
また、インドネシアでビジネスを行っていたら、スカルノ元大統領と第3夫人のデヴィ夫人に近づき、大きな利権を得ていたかもしれない。
しかし、いずれの国を時の政権が代わればそれまでで、君も元大統領、ファーストレディー達と一緒に追放されたかもしれないし、もしかしたら、この世から消されていたかもしれない。
近道をせず、シンガポールで一歩一歩、王道を歩んできたことが、その後に他国に進出したときに応用でき、他の日系企業より一歩先に進むことができたのだと、今では確信している。
続き「第4章」(#7)はこちらからどうぞ

『アジアで負けない三流主義』
ゲーテビジネス新書 幻冬舎

著者:森 幹雄(もり みきお)
クラウンライン・グループ社主・CEO
海外日系新聞放送協会副会長
アジア経営者連合会理事
シンガポール日本人会理事
1953年京都府生まれ。工業高校卒業後、日立製作所入社。退社後、アメリカを経て、単身シンガポールへ渡る。外資系引っ越し会社に3年間勤務後、日本人による日本人のための海外引っ越し専門会社クラウンラインを設立。今では11か国21都市に進出する。本業以外にも出版・情報サービス、イベント企画などを展開中。
アジアビジネス実践塾 www.sg-biz.com
✉:mori@comm.com.sg まで、お気軽にご連絡を!