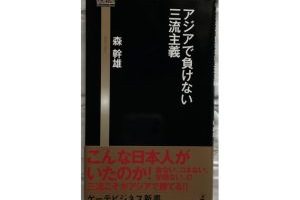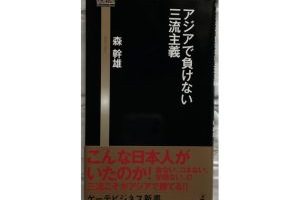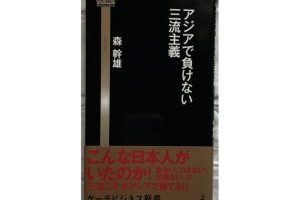2025.04.28
スーツケースひとつを手に海を渡り、シンガポールで海外引越し専門会社「クラウンライン」を創業。ゼロからの挑戦は、今や11カ国21都市への事業展開へと実を結んだ。「金なし、コネなし、学歴なし」⸺“三流”だからこそ勝てたアジアビジネスのリアルを描いた一冊、『アジアで負けない三流主義』。その逆転の極意とは?
前回#3の内容を読みたい方はこちら!
#1から読みたい方はこちら!
第2章 学歴はない方が強い
常に組織の長を狙う
日立の役員を目指す
日立を辞めた理由は、日本の学歴社会の現実をあらゆる面で思い知ったことだ。現在、日本の多くの企業が、成果主義や実力主義を掲げている。しかし、実態は違う。まだまだ旧態依然的で、学歴社会からは脱していない。事実、創業経営者を除くと、高卒や中卒の社長にはまずお目にかかることはない。
1970年代ならばなおさらだ。高度経済成長期の日本では、終身雇用や学歴主義は当たり前の概念だった。それでも、若い私は希望に燃えていた。日立製作所の取締役になるつもりで働いていた。あわよくば代表取締役になってやろうとすら考えていた。
「オレはこの会社の役員になってみせますよ!」上司や先輩たちにも堂々と宣言していた。しかし、私の理想は冗談としか受け取られなかった。
「森、お前、何を寝ぼけたこと言っとるんや。高卒の社員が取締役になるなんて、夢のまた夢。高卒はさんざん大卒のおもりをした後、入社10年もすれば子会社に異動やで。場合によっちゃ、孫会社行きや。そこで定年を迎えるのが高卒の“コース”ってもんや」
悔しかった。そんなはずはない。努力は報われる、と反論したこともあった。
しかし、周囲を見回すと、先輩たちの言うことは実に現実的だった。高卒の社員はみんな大卒のお世話係のような状況だ。そして、夜飲みに行けば会社や上司への愚痴を延延と吐いていた。自分の将来に明るい展望を見ることは難しかった。
長に近づくためにはどんな手でも使え
日立の弁論大会
しかし、夢をかんたんにあきらめる私ではない。学歴や派閥の壁を破る方法を日々考え抜いた。
その案の一つは、労働組合の幹部になることだった。労働組合に入り、書記長や組合委員長になれば、社長と向き合って話し合うチャンスを必ず得ることができる。上層部に自分の存在を強く印象づけられる、と考えたのだ。
私はすぐに行動に移した。労働組合の活動を活発に行い、青年婦人部のトップになった。中部代表として全国弁論大会では全国から集まった社員の前で堂々とスピーチした。
弁論大会で優勝する自信はあった。周囲もそれを認めてくれていた。しかし、結果は予想を大きく裏切った。優勝したのは、労働組合の中核、日立工場の社員。どう考えても私の内容がピカイチだったのに。
「この会社では労働組合にまで派閥が存在するんやな・・・・・・」現実を思い知った。
そんなとき、仕事場で、私にとって決定的な事件が起きる。
会社の名刺に胡坐をかくな
日立に辞表を書く
目の前で、取引先の専務が両手をついて深く頭を下げている。父親と同世代の年齢の人だ。
この会社とは、たびたびトラブルが生じていた。こちらの求める物が決められた期日に納入されず、何度もクレームを出していたのだ。ときには、大声で怒鳴りつけた。それでも改善されず、とうとう最後の切り札を出した。
「長い間取引をさせていただいていましたが、これでもう中止にさせていただきたいと考えています」その時である。相手の専務が土下座と思えるほど深く頭をたれたのだ。
それからほどなくして、その会社から私は接待を受けた。その、ある意味当然と認識して出かけた席で、考え方、生き方を改めさせられることが起きたのだ。専務にとっては不本意な謝罪の席だったのだろう。酔いつぶれた先方の専務が本音を漏らした。
「君みたいな若造に嫌みを言われ、暴言を浴びせられ、プライドをズタズタにされても耐え忍んでいるのは、仕事を失いたくないからだ。うちの社員やその家族を食べさせなくてはいけないからだ」
「君は、日立製作所の森であって、森の日立製作所ではないんだぞ」それらの言葉は私の心に深く鋭く突き刺さった。購買課にいる自分のポジションに知らず知らずのうちに甘えて、有頂天になっていた自分を恥じた。
その専務をはじめ取引先の人たちが若い私に頭を下げ、どんなに厳しい要求にも笑顔を絶やさずにいるのは、私が日立の名刺を持っているからなのだ。誰一人として“森 幹雄”個人に頭を下げているのではない。そんな当たり前のことに気づかずにいた自分が許せなかった。
「名刺から日立のロゴをとったオレは一体何者?」初めて自分に問いかけた。
「資材を仕入れる購買課ではなく、製品を売る営業に異動になったら、立場は逆転して、頭を下げることになるの?」
それを思った時、このままではいけないという結論に達した。
そして、会社に辞表を書いたのである。
自分探しをするために・・・・。
優れた上司は部下の気持ちになれるもの
部下の退社を認める3ケース
辞表は受理された。会社を辞めることを周囲は強く止めてくれたが、上司は受け取ったのだ。
上司が部下の退社を引き留めるには、いくつかのケースがある。
一つ目は、保身だ。
その部下が辞めることで業務が滞ることを避けたいから。面倒な引き継ぎがあり、後任に不安を感じているから。社内的に管理責任を問われることを避けたいから。
二つ目に、善がある。
上司が、自分がいい人であるかのように振る舞うケースだ。
「ほかの会社へ行ってもどこも一緒だぞ」この種のことを言って引き留める。「オレだって辞めたい。でも社会とはこんなものなんだよ」とも言う。このタイプの上司の心の奥には、会社を辞め新しい環境に身を置こうとする者への妬みの感情がある。
そして、三つ目に、相手の身になって考えるタイプ。
辞めようとする部下の力量、退社する気持ちをできるだけ本人の身になって考え、判断し、一時的な気の迷いだと感じたら止める、という健全な上司だ。
そして、私は実に恵まれていた。私の上司は三つ目の、部下の気持ちになって考え、判断してくれる人だったのだ。そのとき、私は、これからは組織の力に頼らない人生を送りたいと心に決めていた。それには自分自身に力がなくてはいけない。だからこそ、ほかの会社へ転職するのではなく、アメリカへ渡り、人生とビジネスを勉強しようと考えていた。それを正直に、ありのまま上司に伝えると、気持ちを汲み、退社を承諾してくれたのだ。
その対応には今もものすごく感謝している。その上司は、後に私がアメリカへ旅立つ際、羽田まで見送りに来てくれた(当時、成田空港はまだ開港していなかった)。さらに、私がシンガポールに渡航して30年を迎えた2007年にはそれを祝う日立のOB会まで開いてくれた。
憧れの人間を目指せ
ロッキー青木の自伝と出会う
なぜ、私が最初アメリカを目指したのかー。
その理由には、まず父親の存在がある。船乗りだった父は、私が子どもの頃、自分が体験した海の向こうの出来事をいつも話して聞かせてくれた。そして、私はいつしか太平洋をはさんだ大きなアメリカへの憧れを抱くようになっていたのだ。
そして、もう一つ、私がアメリカに憧れた理由があった。それは、日立時代たまたま入った書店で手にした本で知った、ロッキー青木さんの存在である。ロッキー青木さんの生き方は、私の心を大きく揺さぶった。それは雷に打たれたような衝撃だった。
ロッキー青木こと青木廣彰さんは、アメリカで鉄板焼きチェーンのBENIHANAを成功させた人物だ。慶應義塾大学在学中にレスリングの日本選抜に選ばれ渡米し、そのままアメリカに残って、路上でアイスクリームを売るところからビジネスをスタート。アイスクリームに紙で作った和傘のミニチュアを飾ったことが、大人気になった。その後、大道芸人的なパフォーマンスで肉を焼く鉄板焼き店へと進展し、アメリカ全土で大ブームに。BENIHANAをアメリカだけではなく、世界で100店舗を超える大チェーンへと育て上げた。
レスリングも続け、全米チャンピオンに。ビジネス成功後にはパワーボートや、気球での太平洋横断などの冒険を行った。今でいうヴァージングループの総帥、リチャード・ブランソンのような人だ。
アメリカのメジャー誌『TIME』の表紙にもなったロッキーさんに、私は猛烈に憧れた。
「オレもこんな男になりたい!」
強く願った。彼の著書『おれの演出行動学』や『ベニハナの挑戦〜アメリカで億万長者になる法」は何度読み返したかわからない。
続き(#5)はこちらからどうぞ

『アジアで負けない三流主義』
ゲーテビジネス新書 幻冬舎

著者:森 幹雄(もり みきお)
クラウンライン・グループ社主・CEO
海外日系新聞放送協会副会長
アジア経営者連合会理事
シンガポール日本人会理事
1953年京都府生まれ。工業高校卒業後、日立製作所入社。退社後、アメリカを経て、単身シンガポールへ渡る。外資系引っ越し会社に3年間勤務後、日本人による日本人のための海外引っ越し専門会社クラウンラインを設立。今では11か国21都市に進出する。本業以外にも出版・情報サービス、イベント企画などを展開中。
アジアビジネス実践塾 www.sg-biz.com
✉:mori@comm.com.sg まで、お気軽にご連絡を!