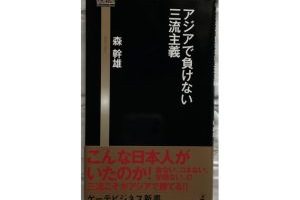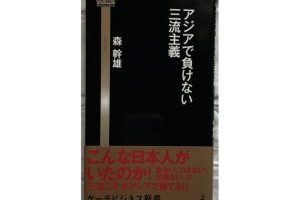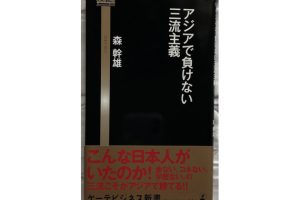2025.04.28
「金なし、コネなし、学歴なし」⸺“三流”だからこそ勝てたアジアビジネスのリアルを描いた一冊、『アジアで負けない三流主義』。引き続きお楽しみください。
前回#4の内容を読みたい方はこちら!
#1から読みたい方はこちら!
第2章 学歴はない方が強い
売るよりも「買いたい」と思わせろ
ブリタニカ営業記
さて、アメリカに渡るとは決めたものの、日立製作所で3年間働いただけでは先立つものはない。そこで渡米のための資金稼ぎとして始めたのが、日本で翻訳版が出版されたばかりのブリタニカ国際大百科事典とその英会話テープのセールスだ。
まずは営業の原理原則を身につけようと、マーフィーやカーネギーの成功哲学の本を読み漁った。そして、そのうえでオリジナリティを加えようと考えた。
百科事典も英会話のテープも、いくらお願いしても、高価なのでそうかんたんに買ってくれるものではない。食料品のように、それがなくては生きていけない必需品とは違うからだ。
だから、それを持つことがいかに得か、いかに素敵な可能性を秘めているかを示せばいいと考えた。自分から「買ってください」とお願いするのではなく、相手が「買わせてほしい」と思う状況をつくることが大切だと思ったのである。
「英会話を身につけましょう」などとは言わず、「これからの時代、英語が話せると、女性にもてますよ。ほかの男性とはすっごく差がつきますよ」とアプローチをするのだ。
こんなことを言った。
「例えば、彼女と洋画を観に行きます。ほかの人は字幕を読みますが、あなたは英語を聞いて、誰よりも早く驚き、感動し、笑い、泣きます。隣の彼女も惚れ直すこと間違いありません」
なんといってもよく買ってくれたのは、30代前半の女性だった。日本が今よりも男尊女卑だった時代だ。実力があっても管理職になれない女性がたくさんいた。彼女たちにアプローチしたのだ。
「職場に外国から電話がかかってきますよね。みんな、困ります。電話はたらい回しです。そんなとき、あなたが突然英語で話してみてください。みんな、びっくりしますよね」
学歴があり、社歴が長くても、お茶汲みばかりの女性が多かった。そういう女性たちが高価な英会話のテープを進んで買ってくれた。
勘どころをつかめば応用を利かせればいい。すぐに1か月の収入は50万円を超えた。セールスを始めて3か月目には西日本で売上ナンバーワンになった。日立時代の月給が6万円なので、かなりの収入だ。
渡米資金の100万円はあっという間にできた。
必要なモノが世の中になければ作れ
オリジナルのスーツケース
日本で海外旅行が自由化されたのは1964年。これは、東京オリンピックが開催され、東海道新幹線の東京・新大阪間が開通した年だ。
このときに定められた海外へ持ち出していい金額はUS500ドル。1ドル=360円の固定相場制だったので、日本円にして18万円だけだ。私が渡米した1974年もまだこの状況が続いていた。円からドルへ、銀行で両替をすると、パスポートに「両替済」というスタンプを捺された。
しかし、これだけではアメリカで生活などできない。だから、闇でドルを買い、腹に巻いたさらしの中に日本円ともども突っ込んで、出国した。
この時期は、まだ市販されているスーツケースも限られていた。アメリカのサムソナイトと日本のエースが技術提携したばかりで、これが目玉が飛び出るほど高価だった。当時はまだキャスターなど付いていない。
そこで、スーツケースは自作することにした。
運よく日立製作所の購買課時代の取引先に、アルミの製造と販売を行っている会社があった。そこで、丈夫なジュラルミンの“箱”を購入し、取っ手とキャスターを付けてもらった。今でこそ当たり前になっているが、当時は実に貴重なキャスター付きスーツケースが出来上がった。
これがアメリカの税関でチェックの対象になった。なにしろ、職員はそれまでに見たことがないのだ。その“特殊なケース”の中に麻薬などが隠されていないか、徹底的に調べられた。

初心を忘れないため、ずっと持っているスーツケース
しかし、そんなものは所持していない。ひと通り調べて問題がないことを確認すると、じっとこちらの目を見て質問を投げかけてきた。
「日本ではこんな便利なボックスを売っているのか?」自作だと答えると、ニヤツと笑って、親指を立てた。「グッド・ジョブ!」とても気分のいい出来事だった。
キャスター付きのジュラルミンのスーツケースを作ったのは、おそらく私が世界で初めてだったのではないだろうか。それが誇らしくて、このオリジナルのスーツケースは今も大切に持っている。
屈辱の体験を忘れない
LAでハウスボーイと皿洗い
アメリカには1974年から1975年にかけて、約1年半滞在。LA(ロサンゼルス)周辺で生活していた。英会話学校へ通いながら、就いた仕事は、裕福な家庭のハウスボーイ、レストランの皿洗い、日本人旅行者のガイド・・・・・・など。
ハウスボーイというのは、聞こえはいいが、炊事、掃除、洗濯、庭の手入れ、ベッドメイク・・・・・・など、家事全般を行う住み込みの使用人だ。LAを一望できる山の上にあり、庭には広いプールもある富豪の邸宅のハウスボーイの仕事にありついた。雇い主は金持ちだがドケチで、黒塗りのキャデラックに乗っているにもかかわらず、毎朝新聞に折り込まれる割引クーポンを利用するためにスーパーからスーパーへとはしごをするほどだった。クーポンの割引よりも燃費が悪い巨大なクルマのガソリン代のほうが高くつきそうだが、使用人の私がそんな指摘ができるはずもない。
ここでの仕事はかなり屈辱的だった。
チリンチリーン。“ご主人様”は用事があると、私の名前を呼ばずにハンドベルを鳴らす。犬を呼びつけるようなものだ。
「イエッサー!」こちらは雇い主のもとへ速やかに参上しなくてはいけない。「イエッス・マダーム」指示をあおぐが、ほとんどの場合、大した用事ではない。
「コーヒー」それだけ命じられる。
チリンチリーン。また呼ばれ、参上する。「もう1杯」そんな毎日だった。
後にシンガポールで起業してから、私はハンドベルのコレクションをした。大小さまざまなデザインの鈴を200近く収集した。なぜか。それは屈辱のハウスボーイ経験を忘れないためだ。困難に出遭い挫けそうになると、鈴を鳴らす。すると、「なにくそ!」という思いが身体の中にみなぎってくるのだ。今、実際にメイドを雇っているが、一度もベルを使ったことはない。
皿洗いの仕事もまた、やりきれない思いだった。
「日本では一流企業で働いていたオレが、なぜこんな店で皿を洗わなくちゃいけないんだ」
皿を洗っていると、考えても仕方がないことを考えたものだ。
あれは店の厨房でジャガイモの皮をむいていたときのことだ。自分があまりにみじめで、悔しくて、切なくて、涙が溢れてきた。ちょうどその時に、シェフが入ってきた。
泣いていることを悟られたくなくて、私はあわてて近くにあった玉ネギを手にした。
「この玉ネギ、目にしみますわ」苦しい言い訳をしたことは今も忘れない。
「オレにはまだ最後のプライドが残されている」あのときそう感じた自分自身にほっとしたものだ。
英語はある日突然しゃべれるものだ
LAの旅行代理店で職を得る
アメリカで最後にありついた仕事は航空会社系の旅行代理店のツアーコンダクターだった。
ビジネス英語が未熟だった時期、私は毎日夕刻になると、サンセット・ブールバードのバーでちびちびとビールを飲んでいた。英会話の勉強と思い、そこの女性バーテンダーとの会話を楽しんでいたのだ。
英語は未熟だったが、アルコールの力を借りると、恥ずかしいという感情が薄れた。バーテンダーも私をちょうどいいヒマつぶしの相手にしてくれていた。
そんなある日、追加オーダーもしていないのに、目の前にすっとビールがおかれた。間違いだと思ってバーテンダーのほうを見た。
「ディス・イズ・オン・ザ・ハウス」彼女はそう言ってウインクした。
少し間をおいて、それがオゴリだということを悟った。私が英語を自由に操れるようになったのはあの瞬間である。
語学というのは、徐々にできるようになるのではなく、努力を続けていると、ある日突然操れるようになるという。脳の回路はジグソーパズルのようになっていて、ある日、最後のピースが埋まるのではないだろうか。その最後のピースが、あの夜のビールだったのだ。
翌日からは、それまでの不自由さがウソのように、滑らかな英語がしゃべれるようになり、周囲の会話がよく聞こえてきた。当然、英語に対するコンプレックスからも解放された。
その結果として、LAのダウンタウンにある旅行代理店での採用が決まったのだ。
ツアーコンダクターの職に就いてからは、さまざまな土地を訪れるようになった。
日本からの旅行者を飛行場でピックアップし、市内観光のアテンドをして、ホテルにチェックインする毎日。アナハイムにあるディズニーランドには、多いときで一日に3回も訪れたものだ。
私のガイドは好評を博した。私を指名する日本人観光客のリピーターが何人もいたほどだ。そのなかには会社の社長さんもいて、私にこう言った。
「君は独立して、自分の会社を興したほうがいい」
あの時期の体験が、サービス業に向いていることを自覚させたと感じている。また、それと同時に、大きな資金も技術もいらないサービス業こそ、会社を興しやすく、社長になれる近道だと確信した。
原点を忘れるな
ロッキー青木の魂を受け継ぐ
アメリカに講在していた1年半の間に、私が憧れて渡米のきっかけにもなったロッキー青木さんのBENIHANAには一度も行っていない。あまりにも当時は貧しくて、鉄板焼きなど食べられる身分ではなかったのだ。
ただ、LAに着いてほどない時期にBENIHANAの店先をうろついたことはある。
もしかしたらその店にロッキーさんがいて、ばったりと出会い、弟子にしてくれるのでは、というずうずうしい期待を持ったのだ。
当然、そんな奇跡も起こらず、虚しく帰国の途に就いた。
アメリカ時代の私の食事は、来る日も来る日もジャンクフードばかりだった。ハンバーガーとホットドッグの日々だ。
2年目に入って、一度だけ贅沢をして、日本食らしきものを食べたことがある。それは、ご飯に油揚げがのったキツネ丼だった。
「紅馬車」という、BENIHANAをもじった名前の店で、オーナーは韓国人だった。
久しぶりの日本の味に、母がよく作ってくれた懐かしの味を思い出し、涙が溢れてどうしょうもなかった。
ロッキー青木さんには、後年、私がアジアでビジネスを拡大してから一度お目にかかっている。タイのバンコクにBENIHANAがオープンしたとき、開店セレモニーに訪れたのだ。
しかし、すでに肝臓がんを患っていて、痛々しいほどにやせ衰えていた。かつてレスリングで鳴らした人とは思えない姿だった。
2008年7月10日、ロッキーさんは69歳の生涯に幕を下ろした。その後、週刊誌に彼の弟さんの手記が掲載になる。それは憎しみに満ちた内容。アメリカンドリームのすべてを否定する記事だった。
どちらが真実なのか、私にはわからない。ひょっとしたら、弟さんの手記が正しいのかもしれない。
しかし、私がロッキー青木さんに憧れたことは紛れもない事実である。残念ながらアメリカでは成果を挙げることはできなかった。しかし、その経験を糧に、今アジアで広くビジネスを展開させている。
ロッキー青木さんのスピリットは間違いなく私の中に受け継がれている。
彼に憧れて海を渡った原点を忘れたことは一度もない。
続き「第3章」(#6)はこちらからどうぞ

『アジアで負けない三流主義』
ゲーテビジネス新書 幻冬舎

著者:森 幹雄(もり みきお)
クラウンライン・グループ社主・CEO
海外日系新聞放送協会副会長
アジア経営者連合会理事
シンガポール日本人会理事
1953年京都府生まれ。工業高校卒業後、日立製作所入社。退社後、アメリカを経て、単身シンガポールへ渡る。外資系引っ越し会社に3年間勤務後、日本人による日本人のための海外引っ越し専門会社クラウンラインを設立。今では11か国21都市に進出する。本業以外にも出版・情報サービス、イベント企画などを展開中。
アジアビジネス実践塾 www.sg-biz.com
✉:mori@comm.com.sg まで、お気軽にご連絡を!