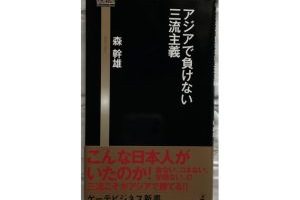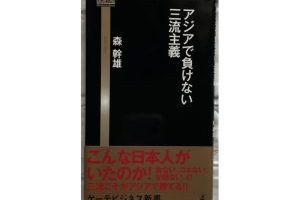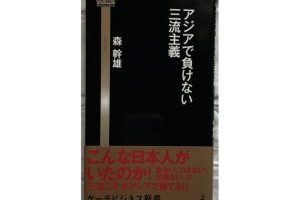2025.03.26
スーツケースひとつで海を渡り、シンガポールで海外引越し専門会社「クラウンライン」を設立し、今では11カ国21都市に進出を果たす。アジアビジネスを成功させるための方法を伝授する一冊の本『アジアで負けない三流主義』を紹介する。金ない、コネない、学歴ないの三流中の三流だからこそ勝負できるという、その極意とは….
これまでの#1,#2の内容はこちらからお読みいただけます!
第1章 お金はないほうが強い
常にニッチを意識する
ボート部主将でインターハイへ
日本にとどまらず、広くアジアを自分のステージとしてビジネス展開するための強靱な身体と心をつくってくれたのは、貧しさゆえ小学校時代から高校時代にかけて毎日行ったアルバイトだけではない。そのほかに、もう一つ大きな体験がある。
それは、高校の3年間エネルギーを注いだ漕艇部(ボート部)だ。このクラブ活動によって、私は、ニッチ、競争相手の少ないところを狙うことの重要性を身を以て知ることになる。
ボートに魅力を感じたのは、父親の影響だった。父は若い頃、外国航路の船員として働いていた。それが父の誇りでもあり、子どもの頃、いつも海の向こうの話を聞かされていたのだ。だから、一時期は、高校を卒業した後、商船大学か海上保安庁に進む夢を持っていた。船という乗り物に対する思い、憧れが強かったのだ。
京都市立洛陽工業高校に入学したとき、野球部やサッカー部に入ることも考えた。しかし、待てよ?考え直した。野球やサッカーのような人気があるスポーツは、当然競技人口も多い。そして、高校までにすでにキャリアを重ね、スキルを上げている同級生がたくさんいる。ましてや道具を揃えるのにもお金がかかる。
そこで、競技人口の少ないクラブに入部することを考えたのだ。そして、ボート部に目をつけた。ボートやオールは学校のものだったので、道具代もかからない。それに、私は即レギュラーになりたかった。1年生だからといって、球拾いや先輩のユニホームを洗ってばかりの生活は、とうてい耐えられるとは思えなかったのだ。
自分が通った洛陽工業高校は、京都駅の隣にある西大路駅の近くにある。しかし、漕艇というスポーツは、当然、水がなければできない。だから毎日、汽車でわざわざ滋賀県の大津まで通っていた。琵琶湖やそこから流れ出る瀬田川で練習を行うためだ。
入学したばかりの時期は、漕ぎ手をやっていた。しかし、これは自分に向いていないことを思い知る。身体的に不利なのだ。漕ぎ手は、身長が高くリーチが長ければそれだけ有利だ。私はそのどちらにも該当しない。そこで、2年生からはコックス、つまり“舵手”をやった。
漕艇部では、1年の夏に力ずくで上級生を差し置いて主将になった。
「鬼の森」近畿地区ではそう言われた。コックスであり、主将でもある、私には誰一人逆らえない状況だったからだ。もちろん、ただ威張っていたわけではない。勝つために、思いつくすべてのことをした。理論に関する書籍を読みこむだけではなく、あらゆる伝手を使って当時最強だった同志社大学と実業団ナンバーワンのチームだった東レの漕艇部の門を叩き、新しい理論の教えを請うた。
自分の高校の先輩たちの考え方は古かった。根性論なのだ。それでは勝てない。私は理論武装で、先輩たちの意見を退けた。努力と創意工夫は、きちんと成果を挙げてくれた。
1年生の時の新人戦では京都府大会で優勝、2年生でインターハイ出場、3年生でインター杯と国体に出場した。私が卒業する時には、洛陽工業高校漕艇部は常勝軍団に育っていた。私が作ったその体質は後輩がきちんと引き継いでくれて、私の次の代は国体2位。そして、ロンドンで行われた国際大会にまで進出した。ちなみに彼らは、私が3年の時、集団退部を企てた面々だ。私は後輩たちに鉄拳制裁を加えることで、退部を思いとどまらせた。しかし、今では彼らに感謝されている。
くり返しになるが、ここで最も重要なのは、ニッチを狙う大切さだ。ニッチだからこそ、ナンバーワンになれる可能性が高く、そこで得られる自信や達成感ほど、人を成長させてくれるものはないのである。
高校に入学したときに、人気があって競技人口が多い野球部やサッカー部に入っていたら、間違いなくこれほどの成果は手に入れていない。どんなに努力を積み重ねても、近所の名門高校あたりに予選1回戦で軽くやられていただろう。競技全体の選手層の厚さがボートとは比べ
物にならない。
野球やサッカーは、小学校や中学校で十分にトレーニングを積んできた者ばかりだ。貧しさゆえアルバイトにいそしんでいた私ではとうてい太刀打ちできなかっただろう。甲子園なんて夢のまた夢だ。その点、高校までに漕艇の経験がある者はほとんどいない。親が漕艇をやっていたか、もしくは、漁師の倅くらいだろう。とはいえ、漁師の船とボートではまったく漕ぎ方が違う。だから、ほとんどの場合は、高校からキャリアがスタートする競技なのだ。だからこそ、ハンディキャップなしで努力をすることができたわけだ。
この考え方は、そのまま社会でも役立っている。私はシンガポールをはじめ、アジア各国で引っ越し業を核にビジネス展開をしている。
日本ではなく、アジアの国であることや、その土地での競合相手が少ないことがビジネスを有利に進めてくれたと思っている。
母の存在は偉大だ
子どもを信じる親の力
さて、この章の最後にどうしても触れておきたいことがある。それは、母親についてだ。どんなに貧しく食べるものに不自由しても、新聞配達や牛乳配達がつらくても、私が挫けずに前向きに育ったのは、間違いなく母のおかげである。
すでに書いた通り、母は裕福な家に生まれ育った。お手伝いさんを雇うほどの家だったらしい。さらに、当時珍しい高等女学校にも通っていた。しかし、17歳の時に結核で両親を失い、財産を親戚に食いつぶされてしまい、一気に貧しい暮らしになった。
母の財産をあてに婿養子になった父が、いつも「オレは森家にだまされた」と言っていたのも、前述した通りだ。しかも、母は、私が小学校4年生の時に重い腎臓病になり、腎臓を一つ摘出している。貧乏、闘病、大酒を飲んでの夫の愚痴・・・・。それでも、母はいつも優しく、明るく、笑顔を絶やさない人だった。そして、私の身になって考え、励まし続けてくれた。裕福だった子どもの頃に憶えたクラシック音楽のメロディをいつも口ずさんでいた。
高校を卒業した後、私は日立製作所へ入社する。大企業だ。父親は手放しで喜んだ。しかし、後で詳しく述べるが、私は3年で日立を辞めた。そして、アメリカへ行くことを決めた。両親に大反対されると思っていた。
しかし、母は違った。
「お前はまだ若い。もっと冒険したらええ。お父さんは反対するやろうから、出発の2週間ぐらい前に言ったらええ」そう言って背中を押してくれた。あの言葉があったから、上司に辞表を提出するときも、まったく迷わずに済んだ。
アメリカで思うようにいかずに戻ってきた私に対して、シンガポールに渡る際も父親が反対する傍らで勇気を与えてくれた。
「お前が海外でやるのは無理や!これからは京都で地道にやれ」父が言うやいなや、母はまったく反対の励ましの言葉をくれた。
「どんなことがあってもシンガポールで夢を実現しなさい。一度や二度の失敗で挫けたらあかんで。頑張り屋さんのあんたなら絶対できる!」
あのときの言葉は決して忘れない。この本を書いている時点で、偉大な母は85歳、大腸がんを患っているが、まだまだ長生きしてほしい。
第2章 学歴はない方が強い
説得は気迫だ
日立製作所入社
工業高校を卒業した私は、日本を代表する一流企業の日立製作所に入社した。入社試験は筆記と面接。しかし、その試験日は漕艇のインターハイと同じ日だった。
どちらをとるかー。
私は迷わずインターハイを選択した。コックスであり、主将である私が不参加では、チーム全体で目指していた大会の優勝の夢は断たれるからである。
「主将として、コックスとして、どうしても僕はインターハイに行かなくてはいけません。面接日を変更していただけないでしょうか」日立の人事の方には、正直に事情を話した。
「チームのため、学校のため、京都のために戦うんです。なんとかならないでしょうか」何度も何度もお願いをしたところ、無謀な提案にもかかわらず、私の希望は受け入れられた。
一人の入社希望者のために大企業が試験日を別に設定するなど、ふつうはあり得ない。しかし、その時の人事担当の方が同じ京都出身だったことが幸いし、こちらの要望に応じてくれたのだ。
もし試験日変更の希望が受け入れられなかったらどうしたか?
もちろん、日立への入社はあきらめた。そのくらいの気迫で交渉したので、思いのほどが相手に伝わったのだろう。
そして、合格。新卒で配属されたのは日立製作所大阪営業所だった。京都の自宅からは京阪電車で約1時間半。大阪の淀屋橋にある営業所
の購買課である。この部署は、大卒の経済学部と高卒の商業系の社員で構成されていた。工業系の社員は私一人だけだ。
「ここは、技術の日立。だから、機械を専門に勉強してきた社員が欲しくて君を採用した」上司に励まされ、毎日気合を入れて出勤していた。
購買課の主な仕事は資材の購入である。鉄鋼品、非鉄金属、チタンなど当時の新金属を発注した。当時、チタンはものすごく貴重な素材だった。宇宙開発でロケットのボデイの一部に使われるなど、用途は限られていた。今は、メガネのフレームやゴルフのドライバーのヘッドにも使わ
れるようになっているが、隔世の感がある。
やりがいは十分だった。JIS(日本工業規格)やISO(国際標準化機構)などの規格を憶え、技術セクションの方に専門の知識の教えを請うた。
また、納期の重要性、何があっても資材を入手せねばならないこと、強引な安値での購入ではなく、価格安定と長期安定調達、そしてWin-Winのビジネスモデルなどが身体の芯まで沁みついた。また、社会人としての基本も叩きこまれた。充実した日々を送った。
しかし、この会社を私はわずか3年で去ることになる。
続き(#4)はこちらからどうぞ

『アジアで負けない三流主義』
ゲーテビジネス新書 幻冬舎

著者:森 幹雄(もり みきお)
クラウンライン・グループ社主・CEO
海外日系新聞放送協会副会長
アジア経営者連合会理事
シンガポール日本人会理事
1953年京都府生まれ。工業高校卒業後、日立製作所入社。退社後、アメリカを経て、単身シンガポールへ渡る。外資系引っ越し会社に3年間勤務後、日本人による日本人のための海外引っ越し専門会社クラウンラインを設立。今では11か国21都市に進出する。本業以外にも出版・情報サービス、イベント企画などを展開中。
アジアビジネス実践塾 www.sg-biz.com
✉:mori@comm.com.sg まで、お気軽にご連絡を!