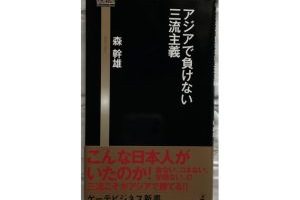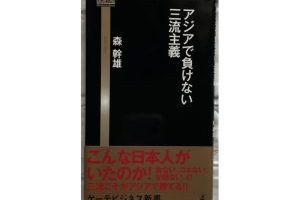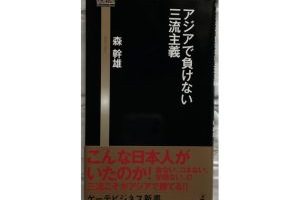2025.01.27
約10年前に執筆された一冊の本がここにある。
1977年にスーツケースひとつで来星し、1980年に海外引越専門会社「クラウンライン」を起業した著者は、いまやアジア11か国に事業を展開する有名実業家に!
変わるもの、変わらないもの….
40年以上経っても、ビジネスの知恵が今も色褪せない理由とは?アジアでビジネスを成功させるための方法とは?金ない、コネない、学歴ないの三流中の三流だからこそ勝負できるという、その極意を著者が惜しげもなく伝授する。
第7章まで綴られた『アジアで負けない三流主義』
いよいよ注目の新連載がスタート!!

『アジアで負けない三流主義』
ゲーテビジネス新書 幻冬舎

著者:森 幹雄(もり みきお)
クラウンライン・グループ社主・CEO
海外日系新聞放送協会副会長
アジア経営者連合会理事
シンガポール日本人会理事
1953年京都府生まれ。工業高校卒業後、日立製作所入社。退社後、アメリカを経て、単身シンガポールへ渡る。外資系引っ越し会社に3年間勤務後、日本人による日本人のための海外引っ越し専門会社クラウンラインを設立。今では11か国21都市に進出する。本業以外にも出版・情報サービス、イベント企画などを展開中。
アジアビジネス実践塾 www.sg-biz.com
✉:mori@comm.com.sg まで、お気軽にご連絡を!
はじめに
「広くアジア全域で人生をかけて勝負する心意気があるヤツ、オレ、森幹雄に連絡をくれ!」ことあるごとに私は話している。
私は工業高校を卒業後、日本の会社で働いたものの、自身の将来に希望を持つことができず、この国で働くことに見切りをつけて海外へ渡った。放浪後、身一つでシンガポールで起業。その会社は今ではアジア各国に展開している。こんな、エリートでもなんでもない自分ができたんだから、私は「アジアで一緒に勝負しよう!」と、自身のブログでもそう呼びかけているわけだ。
現在、私が経営するクラウンライン・グループ・コム・プライベート・リミテッドは、海外専用の引っ越し業務を軸に、倉庫経営、出版・情報サービス、イベント企画、不動産仲介、電子部品商社….などさまざまな事業を展開している。シンガポールを拠点に、日本、中国、台湾、タイ、フリッピン、マレーシア、ベトナム、インドネシア、インド、UAE(アラブ首長国連邦)、米国、グループでの総売上は約42億円(2010年実績)、従業員は306人で、うち日本人は76人だ (いずれも2011年11月現在)。
私が現在、クラウンライン・グループの本社があるシンガポールに渡ったのは、1977年8月。24歳のときだった。
「いきそうな国だな」それが最初の実感だ。マレーシア連邦からの独立を果たし、国じゅうが活力に満ちていたからだ。
「ここで勝負だ」そう思った。
それは、スーツケースたった一つでのスタートだった。お金もなければ、学歴だって高卒。ましてや海外に知人などいるはずもなかった。退路
を断った、ゼロからのスタートだった。
シンガポールに渡る前、私はアメリカで働いていた。1971年に高校を卒業後、日立製作所に就職。日立といえば今も昔も超一流企業。しかし、そこで働き続けることに満足しなかった。日立というブランドではなく、森幹雄個人で勝負したい。そう思って海外へ渡った。アメリカでの生活はVISAの問題で1年半ほどで終了。いったん日本に戻り、今度はオーストラリアで働こうと『ジャパン・タイムズ』を見ていたら、一つの求人広告を見つけた。
「MOVING」シンガポールにあるアメリカ系の引っ越し会社が現地スタッフを募集していた。面接試験を受け、合格。すぐにシンガポールに渡った。
「実は、君は補定の補の補だったんだ。本当に採用したかった応募者が次々と辞退したから君に行ってもらうことになった」出発前に日本オフィ
スのスタッフに言われたことが、現地で働く際の最初のモチベーションになった。
「この野郎、オレなしではどうにもならない会社にしてやる!」心に誓った。それから3年間はがむしゃらに働いた。もちろん、ただ頑張るだけで
はなく、起業を視野に入れて、自分流の創意工夫を行った。
そして、1980年3月、クラウンライン・グループの磯、海外引っ越し専門会社、クラウンラインを創業したのだ。
第1章 お金はないほうが強い
三流主義で退路を断て
赤貧少年時代
「三流主義」。私が作った言葉だ。そして、自分の生き方を象徴している言葉でもある。
私は1953年、京都に生まれた。子ども時代は貧しかった。本当に貧乏だった。だから、小学生の頃から働いた。当然、勉強する時間などない。学業はおろそかになり、成績はいつもクラスでも下から数えたほうが早い位置にいた。
学歴は高卒。それも普通科ではなく、工業高校卒だ。貧しく、学歴も低く、自分で言いたくはないが、容姿はいわゆる二枚目とはほど遠い。
そんな三流中の三流が、汗を流し、涙を流し、時には血を流し、成果を挙げる。これを、自分で「三流主義」と命名したのだ。
しかし、はっきり言おう。三流は強い。失うものが何もないからだ。
くり返しになるが、お金はない。学歴はない。コネはない。女性にはもてない。つまり、一流とは違い、三流は常に退路を断った状況で勝負をせ
ざるを得ないのだ。だからこそ、いつでも、どんな相手にでも全力で挑む。
知恵を働かせて貧しさを吹き飛ばせ
一つの卵を6人で分ける
子どもの頃、うちの暮らしはどん底だった。父親は船乗りをやっていたが、独立して自分で仕事を始めたら「陸に上がった河童」だった。すぐに
行き詰まった。私が小学校3年生の頃だ。その翌年、母親が身体を悪くした。腎臓病だった。二つある腎臓のうち一つを手術で取り除くことになり、その手術費や入院費がかさんで、その日の食事にも困るほどだった。
「オレは森家にだまされた」大酒を飲んで酔っ払っては、父はいつも愚痴をこぼした。父は、母方の森家にやってきた婿養子だったのだ。森家はもともと裕福な家で、母は何不自由なく育った。ところが、17歳の時に両親を続けて失う。森家の財産は、未成年だった母ではなく、親戚が管理することになった。そして、いつのまにか親戚によって使い果たされてしまったのだ。
そうとは知らず、父は森家の養子になった。働かなくても、貸家からの家賃収入で、悠々自適に暮らせると期待していたらしい。ところが、待っ
ていたのは貧困生活だった。
「オレの人生はこんなはずじゃなかった」そう思い続けていたのだ。私は姉二人、妹一人の6人家族の長男。一家は生活保護を受けていて、6人家
族に卵が一つしかないこともあった。一つの卵をといて、水で薄め、メリケン粉と醤油を混ぜて、分けて食べる日が何日も続いたことを憶えている。
あれはきょうだいみんなで親戚の家に泊まりに行ったときのことだ。食事のとき、一人1個ずつ、生卵が出された。私たちきょうだいは、顔を見
合わせた。どうやって食べたらいいのか、わからなかったのだ。
「お姉ちゃん、どうやるの・・・・・・?・」小さな声でたずねた。でも、姉もどうしたらいいのかわからず、おどおどしている。
「一人で1個食べてもええの?怒られへん?」心配になった。結局、その親戚の家の子たちの真似をして、茶碗に盛られたご飯の真ん中に穴をあけ
て、そこに卵を割った。ご飯が鮮やかな黄色に染まる。「どんな味がするんやろう?」期待で興奮した。
あの日の卵かけご飯は、子どもにとってはすごく嬉しい体験だったけれど、そこは今思うと母の財産を持っていってしまった親戚の家だ。
うちは学校の給食費なんてもちろん払えない。「森、給食費、どうした!」担任のイワイ先生にいつも叱られた。恥ずかしかった。クラスには好
きな女の子もいた。その前で言われるのだ。かといって、ないものは払えない。でも、腹は減る。だから、ガツガツ食べる。
「森、お前、今日もただ飯食いやがって!」イワイ先生がまた怒る。でも、私は動じない。というか、動じない態度を装う。そして、またしっかりと食べる。さらに、家で腹をすかせている妹の分もパンを持って帰る。そんな日が続いた。
ある日、いいアイディアが浮かんだ。給食当番をやればいいのだ、とひらめいた。そうすればみんなに感謝されて、先生も叱りづらくなる。
さっそく給食当番に立候補した。当番でみんなに配食していると、誰が、何が好きで何が嫌いかがよくわかる。女の子には小食な子や好き嫌
いが激しい子が多い。だから、彼女たちが食べられないものは、もれなく私がいただいた。給食当番になってからは、堂々と毎日お腹いっぱい食
べた。
みんなには感謝されるし、腹いっぱい食べられるし、当番は一石二鳥だった。
手に入れるまであきらめない
食べ損ねた甘納豆
何も持ってない。この事実は、心の奥底から渇望を生む。
「欲しい!」という気持ちは、私は誰よりも強かったはずだ。「持たない強さ」とでもいうのだろうか。子どもの頃「欲しい!」「欲しい!」と思い続けたことが、その後の人生のエネルギーになった。
あれは、小学校へ上がる前だったと思う。来客があり、手土産に甘納豆を持ってくれたのだが、私は遊びに行っていたか、すでに就寝していた
かで、その間に家族で全部食べてしまった。
自分だけが甘納豆を食べられなかった事実を知った私は泣き叫んだ。母がなだめても、父が叱っても、泣きやまない。「わかった。もう泣く
な!明日の朝、甘納豆、買うてやる。だから、もう泣くな!」根負けした父が言い、5円玉をよこした。
その翌朝のことである。家族みんなが目を覚ますと、私の姿がない。「幹雄はどこへ行きよった!」家のまわりをいくら捜せど、見つからない。
まさか、とは思いつつも、父は自転車をこぎ、バス停にして四つ先にある商店街のお菓子屋を見に行った。すると、朝6時、店の前で私が座り込
んでいた。お菓子屋が開くのを待っていたのだ。
「幹雄、まだしばらくは開かへんから、一度家に帰ろう」父がどんなにさとしても、私は動かなかったという。ひとたび「欲しい!」と思ったら、それを確実に手に入れるまで、私は絶対に納得しないのだ。
それは今も変わっていない。
続き(#2)はこちらからどうぞ